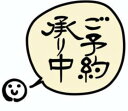ニュース
ウッディジョーの新作木製モデル、より手軽になった「大阪城」と、華やかな江戸の雰囲気を表現した「芝居小屋」【#静岡ホビーショー】
2025年5月16日 18:01
- 【第63回 静岡ホビーショー】
- 会期
- 業者招待日:5月14・15日
- 小中高校生招待日:5月16日
- 一般公開日:5月17・18日
- 会場:ツインメッセ静岡(静岡市駿河区曲金3丁目1-10)
- 入場料:無料
- ※入場には事前登録が必要
ウッディジョーの木製モデルはプラモデルにはない独特の雰囲気がある。一見組み立てが難しそうに見えるのだが、「レーザー加工」により精密に部品を切り出してあるため、ユーザーは組み立てるだけで手軽に精密な木製模型を手にできる。
ウッディジョーは静岡ホビーショーの初日である5月14日に「1/400大阪城」と、「1/120芝居小屋」を発売。2つの新製品を会場でも展示、大きくアピールしており担当者から商品の魅力を聞くことができた。
ユーザーの加工を極力減らし組み立てやすさを重視した「1/400大阪城」
「1/400大阪城」の価格は13,970円。現在、大阪・関西万博で注目を浴びている大阪城がモチーフとなっている。実は大阪城は当時の姿ではない。豊臣秀吉が築城した大阪城は大坂夏の陣により焼失、徳川幕府の二代将軍秀忠が再建した。現在建っているのは、1931年に大阪市民の寄付により復興したものだ。現在の城は鉄骨鉄筋コンクリート造5重8階の高層建築であり、豊臣氏大坂城に盛土し、徳川天守の石垣基礎上に建てられている。初層から4層の白漆喰壁は徳川時代、5層の望楼部分は豊臣時代の金装飾デザインとなっている。
ウッディジョーはこれまで1/150スケールで様々な城をモデルアップしてきた。最新作の「1/150安土城(改良版)」は全高350mmであり、かなり大きく、精密で迫力がある一方で、ファンが複数の城を組み立てると置き場所に困ってしまうといった意見もあり、「もっと小さなサイズの木製モデルも作れるのではないか?」というコンセプトで「1/400大阪城」が決定したという。本商品は全高153mm(飾り台含む)、コレクションしやすいサイズだ。
「1/400大阪城」は"ミニ天守シリーズ"第一弾となる。方向性としても組み立てやすく、エントリーモデルとしての位置づけだ。城には大きいものから、小さなものもあるので、ミニ天守シリーズはスケールを統一せず、モチーフに合わせ手軽なサイズ感を追求していくという。
筆者は先日「1/150安土城(改良版)」を組み立てたのだが、苦労したのが屋根の部分だった。他の部品の多くはレーザー加工によってパーツが成型されており木枠から取り出して組み立てられるのだが、屋根は型紙に合わせ瓦型の木の板を切った上、調整して貼り付け、場所によっては瓶などに押しつけて曲げ癖をつけて貼り付けなくてはいけないため、初挑戦の筆者の安土城の屋根はいくつかの場所でゆがんでしまった。
「1/400大阪城」はこういったユーザーが切り出して調整する要素を極力なくしている。屋根もレーザー加工で表現、貼り合わせるだけで誰でも見本のように精密な木製模型を組み立てることができる。
担当者のこだわりは1層の壁に造型されている銃眼と、石落とし。石落としは壁から出っ張っている部分で、石垣を上ってくる敵兵に上から石を落として対抗するもの。1/150サイズでこれらをきちんと表現できたのはこだわった部分だという。
そして注目ポイントはエッチングパーツの飾り付け。各破風板の飾りに加え、望楼の基部には「虎」と「鶴」を造型したパーツが貼り付けられ豪華な雰囲気を出している。最上層は手すりまで精密に再現されており、その造型技術の精密さに改めて驚かされる。
城の模型は「南側に窓が多い」など、組み立てることでモチーフへの知識が深まるだけでなく、各構造の"必然性"を学ぶことができ、改めて当時の建築技術や、先人の知識のすごさに驚かされる。「1/400大阪城」はそういった要素をより手軽に学ぶことができる。ぜひ挑戦して欲しい。
シールや紙を貼り付け、華やかな雰囲気を演出する「1/120芝居小屋」
「1/120芝居小屋」の価格は10,120円。幅200mm、全高90mmのこちらも手頃なサイズの模型となっている。大阪城と比べると色彩的に非常に豊かで、芝居小屋ならではの派手で賑やかな雰囲気が非常に良く出ている。
開発者は本商品を通じて、「江戸時代の華やかさ」を感じて欲しいという。昔の建物というと色彩が少なく地味なイメージもあるが、江戸時代は派手で華やかな一面があり、その雰囲気が色濃く出ているのが芝居小屋なのだ。派手で賑やかな江戸の要素をこの模型に凝縮したとのこと。
「1/120芝居小屋」で目を惹くのは派手な浮世絵の看板。小サイズながら絵柄ははっきりしており、当時の文化がストレートに伝わる。また書かれた文字も非常に目を惹き、派手だ。商品ではこれらをシールや、和紙にカラー印刷して表現。貼り付けるだけで複雑な浮世絵の看板を作り、模型に飾り付けることができる。市松模様も紙を貼り付けるだけで、塗装したように色彩豊かに組み立てられる。電飾も用意されており、内部にライトが内蔵され、館内から漏れ出る光を表現している。
会場では塗装したアレンジバージョンも展示されていた。こちらには同スケールの人形なども配置されている。これは別売りの「1/150江戸時代の人々」に彩色したもの。アレンジバージョンのこだわりポイントは提灯にLEDを仕込んでいるところ。加工は大変とのことだが、華やかな雰囲気がさらに向上する。
実はモデルアップした「1/120芝居小屋」は入り口の建物で、実際にはこの奥に大きな建物があり、そこが劇場とのこと。ただ劇場は大きい割に密度が低く、模型としての面白みにも欠け、何よりもコストが膨大になってしまうため、文化の象徴として入り口の建物の再現に絞ったとのこと。また、屋根の上の桶は防火用に雨水をためるもので、火事の多かった江戸時代ならではの設備だったり、組み立てることで文化や風俗への知識が深まる商品となっている。こちらも手にして欲しい。



















![マックスファクトリー[Max Factory] ねんどろいどもあ 東方Project ゆっくりしていってね!!! ノンスケール プラスチック製 塗装済みフィギュア 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/41PPbgmtMTL._SL160_.jpg)


![CCSTOYS 鉄魄[MORTAL MIND]シリーズ 『エヴァンゲリオンANIMA』 エヴァンゲリオン弐号機II式 PVC&ABS&POM&PV&合金&マグネット製 塗装済み可動フィギュア 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/41JuZRBeDgL._SL160_.jpg)



![グッドスマイルカンパニー[GOOD SMILE COMPANY] POP UP PARADE ホロライブプロダクション 雪花ラミィ ノンスケール プラスチック製 塗装済み完成品 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/41AvgUzXwaL._SL160_.jpg)






![マックスファクトリー[Max Factory] PLAMAX バニースーツ プランニング BP-03 ソフィア・F・シャーリング ヴァンパイアVer. ノンスケール 組み立て式プラモデル 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51LNCrO43mL._SL160_.jpg)









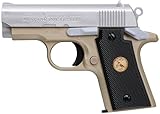

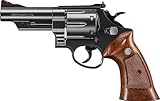
![ベルソス(VERSOS) VERSOS エアーガンセット Colt1911モデル & M4 R.I.Sモデル [ VS-C-M4 ] / M4モデル コルトモデル エアーガンキット エアガン サバイバルゲーム サバゲー アウトドア ブラック 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/417Q7MgkNCL._SL160_.jpg)



![ゴッドハンド(GodHand) 神ヤス! 10mm厚 3種類セットB [#600/#800/#1000] GH-KS10-A3B 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/41SoT5eE7fL._SL160_.jpg)

![武藤商事(Muto Syouji) MUTOSYOUJI [] プラリペア ブラック PL16B【HTRC3】 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/51Hn79+nVuL._SL160_.jpg)




![タミヤ ミニ四駆 GP.453 カーボン強化8Tピニオンギヤ(6個)[15453] 製品画像:18位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/yamada-denki/cabinet/a07000145/7857720013.jpg?_ex=128x128)




![タミヤ ミニ四駆 GP.429 ミニ四駆PRO MSシャーシ用ハイスピードEXギアセット(3.7:1)[15429] 製品画像:13位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/yamada-denki/cabinet/a07000145/7851913015.jpg?_ex=128x128)