レビュー
「1/1000 宇宙戦艦ヤマト3199(第3次改装型:参戦章叙勲式典記念塗装)」レビュー
2024年12月5日 00:00
ヤマトを守る無数の対空砲。組み立て本番は艦橋部から
ここまでの制作時間は約2時間となっている。比較的大きいパーツでサクサク進むのでテンポよくできた。完成度も高く見えづらい部分にまでこだわったキットだと感じた。続いて艦橋部分になるが、ここからが本番という感じだ。
今までのレビューで艦橋部分の細かさが伝わったと思う。やはりヤマトのプラモデルは一筋縄ではいかなかった。細かい作業が得意な筆者なのだが、慣れないこともあり何度か心が折れかけた。しかしここまで作り上げた時の感動はどのキットよりもあった。ここまで細かいパーツで織りなすヤマトの全景を早く見たいと思い作業を続けることができた。
発進!宇宙戦艦ヤマト!
以上でプラモデル「1/1000 宇宙戦艦ヤマト3199(第3次改装型:参戦章叙勲式典記念塗装)」が完成した。付属の水転写式デカールを貼り付けることで、宇宙戦艦ヤマトの「第3次改装型:参戦章叙勲式典記念塗装」を、貼らなければ「第3次改装型」の姿を再現できる。まずは前後左右から見ていこう。
詳細に見ていくと本キットのヤマトに対する解像度の高さを見ることができる。ヤマト独特の丸みと鋭いパーツが様々な箇所に使われているからメリハリのあるデザインになっているのだと感じた。ここまで作るのは大変だったが、この完成度の高さがあるからだと納得することができた。イメージカットを見ていこう。
付属の水転写式デカールで主砲・副砲各砲身先端にある3本線の参戦章、船体各部に勲章をモチーフとした錨マークを再現している。
組みやすさと完成後の満足感の高さ実感できる逸品!
「1/1000 宇宙戦艦ヤマト3199(第3次改装型:参戦章叙勲式典記念塗装)」は非常に満足度の高いプラモデルだった。艦橋の完成度の高さにフォーカスしたが、ボディの方も組みやすくかなり良く仕上がっていると思う。スナップキットだが、今回艦橋パーツでは一箇所接着剤を使うことになった。かなり細かなディテール再現がなされているキットなので、念のため接着剤を用意してから取り組むと役立つ場面もあるだろう。
さくさくと組み進められる船体の面白さと、後半の艦橋パーツの製作では細かなパーツの扱いといった艦船モデル製作の一端を味わえる。比較的難易度の高い部分もあったが、自分で乗り越えてこその感動を味わえる今回のキットに大満足した。艦船モデルと聞くと難しいイメージを受ける人も多いだろうが、このキットはそういった人の入門にも適している。是非この機会に挑戦していただきたい。
(C)西﨑義展/宇宙戦艦ヤマト3199製作委員会



























































![CCSTOYS 鉄魄[MORTAL MIND]シリーズ 『エヴァンゲリオンANIMA』 エヴァンゲリオン弐号機II式 PVC&ABS&POM&PV&合金&マグネット製 塗装済み可動フィギュア 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/41JuZRBeDgL._SL160_.jpg)

![グッドスマイルカンパニー[GOOD SMILE COMPANY] POP UP PARADE ホロライブプロダクション 雪花ラミィ ノンスケール プラスチック製 塗装済み完成品 製品画像:8位](https://m.media-amazon.com/images/I/41AvgUzXwaL._SL160_.jpg)








![マックスファクトリー[Max Factory] PLAMAX バニースーツ プランニング BP-03 ソフィア・F・シャーリング ヴァンパイアVer. ノンスケール 組み立て式プラモデル 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51LNCrO43mL._SL160_.jpg)











![ベルソス(VERSOS) VERSOS エアーガンセット Colt1911モデル & M4 R.I.Sモデル [ VS-C-M4 ] / M4モデル コルトモデル エアーガンキット エアガン サバイバルゲーム サバゲー アウトドア ブラック 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/417Q7MgkNCL._SL160_.jpg)
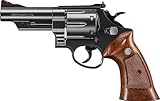




![ゴッドハンド(GodHand) 神ヤス! 10mm厚 3種類セットB [#600/#800/#1000] GH-KS10-A3B 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41SoT5eE7fL._SL160_.jpg)
![武藤商事(Muto Syouji) MUTOSYOUJI [] プラリペア ブラック PL16B【HTRC3】 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/51Hn79+nVuL._SL160_.jpg)




![【中古】[PTM] HG 1/144 シャリア専用リック・ドム(GQ) 機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ガンダム ジークアクス) プラモデル(5072018) バンダイスピリッツ(20260207) 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/6313/0/cg63130988.jpg?_ex=128x128)
![1/24 HKS スカイライン (スカイラインGT-R [BNR32 Gr.A仕様] 1993 SUGO 300km ウィナー) 【20670】 (プラモデル) 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6700/4967834206700.jpg?_ex=128x128)
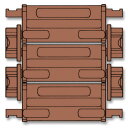


![MODEROID 機動警察パトレイバー ARL-99ヘルダイバー 1/60 プラモデル(再販)[グッドスマイルカンパニー]【送料無料】《07月予約》 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/amiami/cabinet/pb/2026/071/toy-rbt-9237.jpg?_ex=128x128)
![【中古】[PTM] プレミアムバンダイ限定 HG 1/144 ベギルベウトルシュ(ケナンジ小隊所属機/リドリック小隊所属機) 機動戦士ガンダム 水星の魔女 ヴァナディースハート プラモデル(5067261) バンダイスピリッツ(20241025) 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/6312/7/cg63127364.jpg?_ex=128x128)




![【中古】[FIG] S.H.Figuarts(フィギュアーツ) 真骨彫製法 仮面ライダーアギト グランドフォーム 完成品 可動フィギュア バンダイ(20150822) 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/6124/7/cg61247203.jpg?_ex=128x128)


![『グリッドマンユニバース』ZOZO BLACK COLLECTION 「2代目」 完成品フィギュア[ユニオンクリエイティブ]【送料無料】《発売済・在庫品》 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/amiami/cabinet/pb/2024/291/figure-173164.jpg?_ex=128x128)







![ECOS-O Micro Gen3用 フリップアップ レンズキャップ ブラック◆T2仕様 パドラーキャップ[全国一律300円配送可能] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/military-base/cabinet/a/item14/h0935bb.jpg?_ex=128x128)



![【戦人】ロックケースL用トートバッグ[senjin 陸上自衛隊 自衛隊 迷彩 戦人 Senjin ミリタリー アーミー タクティカル サバゲー アウトドア バッグ バック 手提げ 洗面具] 製品画像:20位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/shop-senjin/cabinet/senjin/bag/7102_1.jpg?_ex=128x128)
![ノーベルアームズ マウントベース M4用 ショート [ ハイ ] NOVEL ARMS エアガン 電動ガン ガスガン サバゲー装備 ミリタリーグッズ サバイバルゲーム low high トップレイル トップレール 20mmレール 20mmレイル ピカティニーレール ピカティニーレイル ウィーバーレール 製品画像:19位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/revolut1/cabinet/c93/1_n561_600.jpg?_ex=128x128)










![ジョーゼン 1/22トヨタランドクルーザー70 22トヨタランドクル-ザ-70 [22トヨタランドクル-ザ-70] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/edion/cabinet/goods/ll/img_298/4897039352622_ll.jpg?_ex=128x128)
