トピック
子供も大人も楽しめる! トイザらス新戦略キーマンインタビュー
皆が訪れたくなる場所を目指した新店舗・京都駅前店のコンセプト
- 提供:
- トイザらス
2023年12月28日 00:00
皆が集まれる楽しい場所を目指す京都駅前店
――この新戦略のモデルケースとなったのが、京都駅前店とのことですが、これまでの店舗とはどんなところが違うんでしょうか?
立原氏:まず写真を見ていただきたいです。「マーベル」、「トミカ」、「プラレール」、「任天堂」などブランド・テーマに合わせてコーナーを作り、通路を広くしてお客様がスムーズに目的の商品に行くことができるように考えています。お客様が入口に入ってお店を見渡すと、目的地がわかるようにしました。大きなマーベルのフィギュアなどを看板として使っているのもわかりやすさになっていると思います。
従来のトイザらスは、アメリカのスーパーマーケットのようにジャンルで商品を分けた上で棚の商品を積み上げていくイメージで、お店に入ってもどこにどんな商品があるか、明確にお目当てのブランドがどこにあるかがわかりにくかった。お客様に"気づき"を提供することを意識しました。京都駅前店のレイアウトは「スーパーのような展示方法は本当に玩具の展示として良いのか、玩具を買いたくなるレイアウトなのか」というこれまで社内で議論されていた問いかけへの回答の1つです。
京都駅前店ではV字型の陳列棚も特徴です。この形にするとコーナーとして独立できるし、どんな商品を置いているかぱっと見てわかりやすい。しかもこの内側は玩具を触れる試遊コーナーなど遊んで楽しい空間も兼ねています。
この置き方では従来の配置より品数そのものは少なくなります。ただ従来の店舗の盛りだくさんの玩具の配置は、多くのお客様の総合的な需要には応えられるけれども、お客様1人1人の欲しいものを置いているか、見つけやすいかという所では疑問がありました。京都駅前店のレイアウトはお客様が欲しい商品にアクセスしやすい環境になっています。
その上で広くスペースをとったところに、テーブルと椅子を置いて親たちが休憩できるスペースを設けました。ここで子供と遊んでも良いですし、飲み物やアイスを食べてもいい。京都駅前店の特徴としてアイスクリームやコーヒーの自動販売機の設置を行っています。
これまでも子供が遊ぶスペースはありましたが、そこからさらに一歩進み、子供達が交流できるスペースも作りました。またV字型陳列だけでなく、試遊コーナーもこれまで以上に力を入れ、より多くの玩具を実際に遊べるようにしています。
「来て、目的の玩具を買って帰る」、トイザらスはそれだけのお店じゃなくて、なんとなく来てもらう。今までのおもちゃ屋さんって親にとっては「来るのは限られた時だけ」だったと思うんです。おもちゃ屋に来ちゃうとついつい予定外の買い物をしてしまいますからね。でもそうじゃなくて、遊びに来る場所、来てみて、遊んで楽しい場所にしていきたいと考えています。
実際、京都駅前店は高校生や中学生が学校帰りに寄ってくれるお店になっているとのことです。幅広い層のお客様が来てくれる場所になって、口コミでさらに来てくれるお客様が増えている。そういう実感も持っています。
――これまでのトイザらス店舗とは様々な点が違っていますね。準備期間もかかり、コストもかかったのではないでしょうか。
立原氏:およそ店舗開店まで準備は4カ月、かなりの突貫作業でスタッフにはかなり負担がかかりましたし、コストもかかりましたが、京都駅前店での施策は今後の店舗を如何するかというところで多くのデータとノウハウをもたらしてくれると思っています。私たちとしても大きなチャレンジになりました。
ただ、単純に大人向け商品を多く取りそろえたとか、今回満足できる品揃えを実現できたかと言えば、そうではありません。今回の私たちの品揃えがお客様を満足させたか、どういう商品を店舗に並べればより受け入れられるかは、やはり1つ1つ時間を掛けて試し、評価していただくしかありません。こういったデータはさらに深掘りし、より喜ばれるコーナー作成、品揃えはどうすべきなのかという点を検証していきたいと思っています。まだまだ進化の余地があります。
また、合成スポンジ製のダーツを撃ち出す「ナーフ」ですが、14歳以上対象の「ナーフ PRO ジェルファイヤー」シリーズを販売しました。ダーツの代わりにジェルボールを使用し、目を保護するゴーグルもついています。こちらは日本ではトイザらスが先行して販売しました。
昨今、明確に大人向けのハイエンドな商品が増えている現状があります。我々は玩具を扱うエキスパートとして、今後対応しなければいけないとも考えています。その中でのトイザらスの強みはグローバルであること。アジアで情報を共有するだけでなく、海外の商談会で直接仕入れてくるケースもあります。米国の玩具メーカーとアジアグループで手を組んでビジネスが展開できるというのは、日本の市場においても大きなアドバンテージだと思っています。
もう1つ、玩具というのは新発売を追いかけるだけではなく、既に販売されているものも気付かれていないというか、ポジショニング次第でお客様に注目される。そういうものを集めるショップ戦略もアリなんじゃないかと個人的には思っています。
――京都駅前店の実際の反応はどうだったでしょうか?
立原氏:新しいレイアウト、大人向け商品の拡充を行った京都駅前店ですが、私たちは最初「口コミで徐々に人気を得ていくのかな」と予想していたのですが、意外と見つけてくれて学校帰りの学生達が寄ってくれたり、奥にあるコーナーにもきちんとお客様が来てくれて、目的のものを見つけてくれている。もちろん未だ未だこう言った流れは必要なのですが、予想したよりは多く、手応えを感じています。みんな情報を得るのが早いと感心しています。
こういったお客様の流れは「トイザらスがこういう事をはじめました」と広告を打っても効果は薄いです。学校での口コミや、SNSなどユーザー同士でのコミュニケーションで広がっていくと思っています。私たちもTikTokなどでも含めアンバサダーの方々と協力し、発信もトライアルとして行っています。
――京都駅前店ははっきりとコンセプトを打ち出していますが、広告などでこのコンセプトを宣伝せず、お客様に感じて欲しいという方針とのことですが、テーマを打ち出すところと、あえて主張しない部分のバランスはどのように意識なさっていますか。
立原氏:これは会社と私の考えの半分半分だと思いますが、「ブランドから過度の情報発信は良くない」と思っています。例えば「めいっぱいクリスマスしよう」というメッセージは良いです。でも「Funkoを買いにトイザらスに行こう」、「大人向け商品を強化!」とこちらからいっても伝わらない。
むしろ、そういう情報はお客様同士のつながりから、情報として発信、交換されることに価値があると思っていますし、何より信憑性が高いメッセージだと思います。ユーザーさんに信頼してもらって拡げられるか、そこが勝負所だと思っています。
お客様にきちんと感じてもらいたい。これを実現させるには店側からメッセージを放つのではなく、陳列の仕方、売り方、店頭でのお客様対応など店側の受け皿がちゃんとしなければお客様に信頼していただけない。来ていただいたお客様の期待値以上の体験をしてもらう、これがなければいけない。店員の教育という観点ではここを大事にしています。まだまだ良い意味で固まってないので、各店舗担当者のやりたいことを積極的にやっていこうと思っています。失敗しても学んで、進化させていきたいです。
次ページではイベントなど全国のトイザらスでの新施策について質問していきたい。







![CCSTOYS 鉄魄[MORTAL MIND]シリーズ 『エヴァンゲリオンANIMA』 エヴァンゲリオン弐号機II式 PVC&ABS&POM&PV&合金&マグネット製 塗装済み可動フィギュア 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/41JuZRBeDgL._SL160_.jpg)




![グッドスマイルカンパニー[GOOD SMILE COMPANY] POP UP PARADE ホロライブプロダクション 雪花ラミィ ノンスケール プラスチック製 塗装済み完成品 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/41AvgUzXwaL._SL160_.jpg)





![マックスファクトリー[Max Factory] PLAMAX バニースーツ プランニング BP-03 ソフィア・F・シャーリング ヴァンパイアVer. ノンスケール 組み立て式プラモデル 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/51LNCrO43mL._SL160_.jpg)












![ベルソス(VERSOS) VERSOS エアーガンセット Colt1911モデル & M4 R.I.Sモデル [ VS-C-M4 ] / M4モデル コルトモデル エアーガンキット エアガン サバイバルゲーム サバゲー アウトドア ブラック 製品画像:8位](https://m.media-amazon.com/images/I/417Q7MgkNCL._SL160_.jpg)






![ゴッドハンド(GodHand) 神ヤス! 10mm厚 3種類セットB [#600/#800/#1000] GH-KS10-A3B 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41SoT5eE7fL._SL160_.jpg)
![武藤商事(Muto Syouji) MUTOSYOUJI [] プラリペア ブラック PL16B【HTRC3】 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/51Hn79+nVuL._SL160_.jpg)







![【中古】[PTM] メガミデバイス×フレームアームズ・ガール 1/1 バーゼラルド Animation Ver. プラモデル(FG087) コトブキヤ(20210528) 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/6312/9/cg63129343.jpg?_ex=128x128)


![BANDAI SPIRITS 2720191 HG グスタフ・カールOO型 機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ [プラモデル] 製品画像:5位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/a-price/cabinet/pics/1090/4573102720191.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[PTM] プレミアムバンダイ限定 RG 1/144 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン (最終決戦仕様) [スペシャルコーティング] 機動戦士ガンダムUC(ユニコーン) プラモデル(5065290) バンダイスピリッツ(20250220) 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/6312/4/cg63124825.jpg?_ex=128x128)


![【中古】[FIG] マキマ チェンソーマン CHAIN SPIRITS vol.3 フィギュア プライズ(2615494) バンプレスト(20230430) 製品画像:16位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/6603/1/cg66031087.jpg?_ex=128x128)


![【中古】[FIG] ROBOT魂(SIDE MS) Hi-νガンダム 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン 完成品 可動フィギュア バンダイ(20140118) 製品画像:13位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/6124/7/cg61247559.jpg?_ex=128x128)




![【中古】[FIG] POP UP PARADE(ポップアップパレード) 五条悟(ごじょうさとる) 呪術廻戦 完成品 フィギュア グッドスマイルカンパニー(20220522) 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/6122/6/cg61226085.jpg?_ex=128x128)

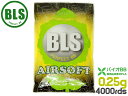





 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/hobby-online/cabinet/_rc/kawada-2/4946649037853-1.jpg?_ex=128x128)
