特別企画
第11回「#遊戯王」宇宙最強カード列伝! 遊戯王を支え続ける壺シリーズの元祖「強欲な壺」と愉快な仲間たち!
2024年5月27日 00:00
- 【強欲な壺】
- 1999年5月27日 登場
爆アドォォォ!アドえもんです!筆者は普段YouTubeにて遊戯王を中心にカードゲーム動画を投稿している愉快でうるさいオジサンだ。
今回もウルトラ歴史を持つ「遊戯王」カードの中で特に名高い連中を生まれた日に合わせて紹介する企画「宇宙最強カード列伝」第11回をやっていこう!
今回のカードは「遊戯王」を代表する古の最強禁止魔法カードの1枚! OCG・アニメの両方で活躍した歴史を持ちつつ、後年では様々な類似カードが生まれたり特殊なルール下では使用可能になったり等、今でもプレーヤーと公式の両方から愛されているカードだ。それでいて今まで紹介してきた連中と違い、禁止解除される可能性が0.000000001%も無いと誰もが感じている摩訶不思議な存在でもある。
そんな25年前の今日、1999年5月27日に発売「Vol.3」にて登場した「強欲な壺」が本日の主役カードになるぞ!
「強欲な壺を発動!!! 俺はデッキから……カードを2枚ドローする!!!」
初代TVアニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」から「GX」のアニメシリーズを見ていたプレーヤーが1度は聞いたことがあるし言った事もあるこのカードの効果!
シンプル過ぎる最初期のカードの中でも特に認知度が高く、禁止カードながら「死者蘇生」に並んで遊戯王を代表する魔法カードと言っても過言ではない。アニメでは展開上、手札が足りなくなった時はとりあえず「強欲な壺」! まだ足りなかったら「天よりの宝札」! 主人公だし「E・HERO バブルマン」でも引かせちゃう! というのが通例だった。
今回の記事ではこの「強欲な壺」が遊戯王界でどのように活躍したのかを振り返りつつ、遊戯王というゲームの特性上なぜこのシンプルな効果が絶対許されないのかを改めて考えてみたいと思う。現代遊戯王プレーヤーなら感覚的に禁止解除はあり得ないと理解できていても、意外とその理由を言語化するのは難しいかもしれないからだ。
また前回に引き続き、このカードも解除された際の活用方法を考えるだけ無駄なので、後半では現代で活躍しているこのカードの後継者たちや愉快な仲間たちについて取り上げたいと思う。それではやっていこう!
使えるならガン積みしない理由がマジでないシンプルパワー!“ノーコストで2ドロー”というカードゲームの常識を打ち破った存在
まず初めに件のカード「強欲な壺」のテキストをチェックしていこう。とは言えその効果は本当にシンプル。デッキからカードを2枚ドローする。以上だ。……短けぇ!
改めてこのカードがなぜ最強たるかを説明しようとすると意外と難しいのだが、あえて言うのであれば数多のカードゲームの中でも特に独自性の強いルールを持つ“遊戯王”の中で「ノーリスク・ノーコスト・ノー条件」で簡単に手札を増やせるからという感じだろうか。
順番に紐解いていくとまず遊戯王というゲームは、多数存在するカードゲームの中でも特に非常にスピード感のあるゲームだと筆者は思っている。
遊戯王には「マジック:ザ・ギャザリング(MTG)」(ウィザーズ・オブ・ザ・コースト)や「デュエルマスターズ」(タカラトミー)のような俗に言う“マナ”の概念が無い。そのようなルールであるため、1ターン内で使用できるカードアクションが格段に多いのだ。故に最序盤からエキサイティングなカードの攻防が楽しめるという点も遊戯王の魅力なのだが、このスピード感の強いゲーム性は手札1枚の価値が凄まじく重いという特徴がセットで紐付く事になる。他のTCGなら序盤は最終的な合戦の準備をするために手札や場を整える時間がある中で、遊戯王は最初からクライマックス状態な事が多いため、最初の5枚の手札に相当命が掛かっているのだ。これは特にゲームスピードが増した現代遊戯王であればあるほど顕著に感じる部分だろう。
そんなカード1枚の重要度が非常に高いゲーム性にも関わらず、「唐突にカードを1枚増やせる(「強欲な壺」1枚を使って2枚ドローするため手札はトータルで1枚増える)」という行為がどれほどヤバい事かは説明不要だと思われる。現に今回はわかりやすい説明のために現代遊戯王も引き合いに出したが、このカードが3枚使用できた時代は2000年4月1日の改定までと僅か1年足らずであり、禁止カードにぶち込まれたのが2006年3月と現代遊戯王のカードパワーにほど遠いカードプールのタイミングだ。しっかりターンを跨いでアドバンテージを稼ぎ合う古の低速デュエル環境であっても「手札1枚を無償で増やせる」という行為が勝敗に強く影響が出てしまうレベルだったことからも、遊戯王におけるカード1枚の重みは凄まじいのである。
もっとも現代遊戯王をプレイしている人ならばこのカードが如何にイカレてるかは直感的に理解できるだろう。先行でこのカードを使えれば後攻1ドローのアドバンテージを帳消しにでき、あまつさえ「墓穴の指名者」や「灰流うらら」などの手札誘発をケアするタイプのカードを引くことができる可能性が生まれるのだからヤバイなんてもんじゃない。ただでさえ現代遊戯王はカードパワーのインフレによって1枚のカードのバリューが凄まじい事になってる状況なため、おいそれと簡単にハンドを増やす行為が許される訳がないのである。
オマケにただでさえ単体カードパワーのヤバイ連中がゴロゴロいる中で、無償ドロー効果は実質的にデッキ枚数を減らせる事に繋がり、デッキの安定感はさらに向上する事となる。その点だけ抽出すれば「成金ゴブリン」や「三戦の才」など現代でも多少代用が効いている存在もいるが、ドロー面に関してはやはり「強欲な壺」のパワーと汎用性を全く超えられないため、格の違う史上最強カードと認めざるを得ない。
次に「ノーリスク・ノーコスト・ノー条件」という部分についてだが、コレについては遊戯王が特別スピード感の早いゲームだからこそ、リスクなく2ドローできるカードが生まれたのかもしれない。数多のカードゲームに触れて来たが、未だかつてここまで何のコストも無く簡単に2ドローできる存在を筆者は他に知らないレベルだ。
歴史の長い人気カードゲーム「MTG」の最強古代カード群「パワー9」が1つ「Ancestral Recall(通称:アンリコ)」ですらしっかり1マナを支払って3ドローなのだ。ゲーム性が違うとはいえ基本どんなカードゲームでもアドバンテージを稼ぐ行為には何かしらコストや条件がつく中、マジで何もなしなのは本当にこの「強欲な壺」ぐらいだ。恐らくどんなカードゲームに登場したとしても余程手札に依存しないゲームでない限り爆速で禁止になるのが「強欲な壺」というカードの強さなのだと筆者は一生感じている。
この「何の条件も無しに」という部分は「強欲な壺」が禁止カードになってからの後輩カード達がその異常性をより顕著にしている。壺が亡くなった後、入れ替わりで規制緩和された「天使の施し」は壺と同じく“何の条件も無しに”系カードだった事で当然ながら翌年に爆速で禁止カードになり、次の世代のドローエンジンとなった「闇の誘惑」や「トレード・イン」は手札枚数は増えない、かつ特定のカードを消費しなければ発動できないorデメリットが発生するといった少し条件が課されたスペックとなっている。
時代が進みカードパワーが上がった事で、むやみやたらに手札を増やせることの危険性が増したのもあるが、壺と違って使用できるデッキタイプに条件がついたことで戦略の幅が広がったのは魅力的な変化だったと感じている。そんな調整が為されたカードである「闇の誘惑」ですら強すぎて一時期準制限になったんですけどね!
さらに時代が進んでいくと「壺」カード達にも続々と実用的な後継者が現われ始める。一時期はカジュアル遊戯王界隈で引っ張り凧だった「貪欲な壺」は墓地からモンスターを5体戻すという重い条件の代わりに「強欲な壺」と同じく2ドローできる点が評価された。次に頭角を現わした「強欲で謙虚な壺」は手札も増えずそのターンの特殊召喚もできなくなる誓約がつく代わりにデッキトップ3枚から好きなカードを回収できるという独自の強みを獲得していた。どちらも採用されるデッキや使い勝手は違えど「強欲な壺」の後継者として長く愛されているカードと言える。
ガッツリ現代遊戯王まで時代を進めると今でもお馴染みの連中が登場する。条件を付ければ2枚ドローさせても大丈夫と思ったのか、デッキのカードを大量に除外してしまう「強欲で貪欲な壺」を皮切りに、2ドローできる代わりにEXデッキのカードを大量に除外する「強欲で金満な壺」が登場するなど、最近の(もう最近でも無い)壺カードはしっかり手札枚数を増やしてくれる印象だ。その特性上入るデッキを選ぶため「強欲な壺」ほどの汎用性は無いが、条件がマッチしたデッキではオリジナルと同等レベルの活躍が可能となっている。
そして直近で登場し、現在最も使用されている「金満で謙虚な壺」はEXデッキを任意の枚数除外する代わりに、その枚数に応じたデッキトップを確認して1枚を手札に加えるという何とも現代遊戯王のニーズにピッタリな能力を持っていたのも印象的。類似カードの「強欲で謙虚な壺」と異なり特殊召喚に制限もつかないため、ありとあらゆるデッキで採用が可能であり、1枚で宇宙コンボを発生させる初動カードや、余裕がある場合は相手の手札誘発を叩き潰せるカードを引っ張れたりなどその強さは今更語る必要も無いだろう。
「強欲な壺」と比較してそれぞれデメリットやクセはあれど、逆にオリジナルには無いメリットも生み出せるようになっているのは美しいポイントだ。
とはいえ現代を代表するこの3つの壺はOCGだと「強欲で貪欲な壺」と「強欲で金満な壺」が準制限カード、「金満で謙虚な壺」が制限カードに入っている状態である。「マスターデュエル」でもそれぞれ独自の規制がかけられている事に加え、「強欲で謙虚な壺」すらも制限カード入りしている。こいつらよりも超手っ取り早く手札を増やせる「強欲な壺」……やっぱ絶対帰ってくることねーわ!!!
愉快な壺の仲間たち! 古くから愛され続ける壺カード達(?)を紹介!
さてここまで何度も何度も言った通り今回の主役「強欲な壺」は禁止解除が100%あり得ず、前回取り上げた「ソウル・チャージ」以上に特徴的な使い方が存在しないカードなので、ここからは“あえて実用性のない”面白壺サポート軍団を少し紹介して記事を閉めようと思う。
最初に取り上げたいのは「強欲な壺」が禁止カードになる前に生まれたサポートカードだ。「強欲な壺」が禁止になって以降、マジで使い道が消えてしまった(意味不明)カードがなんと3種類も存在する事はご存じだろうか。
まず1枚目は「壺盗み」。「強欲な壺」の発動時に発動できる専用の速攻魔法で、その効果を無効にして代わりに1ドローできる効果となっている。なるほど「強欲な壺」が大流行してた時はこのカードを使って相手の壺をメタしてたんですね!
……なんて訳は無く、このカードの登場は2002年発売のパック「黒魔導の覇者」だった事で当時既に制限カードになっていた「強欲な壺」のピンポイントメタカードがメチャクチャ遅れて生まれてしまった背景を持つ。冷静に考えてピンポイントでメタして得られるアドバンテージが1枚ドローなのは流石にメリットが釣り合って無い。というかもっと最初期に生まれたピンポイントメタである「避雷針」や「グリフォンの翼」ですら無効にした効果を跳ね返せてるんだからせめて2ドローしろ!
残る2枚の専用サポートカードはなんとモンスターになる。しかも「壺盗み」とは異なりこちらは少しやる気を見せているから安心して欲しい。
1体目は「強欲な壺の精霊」。「強欲な壺」が発動した時に効果を発動し、発動したプレーヤーがさらにもう1枚追加でドローできるという能力を持っている。召喚して場に残した上で相手が万が一「強欲な壺」を発動したら相手も得をするという部分で少し頭が痛くなるが、基本自分のターンに出して使うのだから問題ないと当時判断されたのだろう。
2体目は「壺魔人」で、こちらも「強欲な壺の精霊」と同じような効果を持っている。手札から「強欲な壺」1枚を墓地に送る事で2枚ではなく3枚ドローを可能とする。「強欲な壺の精霊」と異なり相手に追加でドローされる心配はないためコチラはかなりマトモに見える。
が、冷静に考えるといずれも3ドローする代わりに自身を場に出す手間が発生しているため実質的なアドバンテージ枚数は変わっていない。なにより仮に「強欲な壺」デッキが存在していたとしてもこれら2体の効果発動条件が違うため、場に「強欲な壺の精霊」と「壺魔人」の両者が揃っても特に利点が無いのが面白い。なんで片方は発動時で片方は捨てて発動なんだろうか……。元となる「強欲な壺」が最強カード過ぎた故に周りのカードは面白おかしく作られてしまったのではと筆者は思っていたりする。
そんな禁止化する前から愛されていた「強欲な壺」だが、現代でもその愛されっぷりは健在である。優秀な後輩カードが生まれるのは勿論、様々なタイミングでカードの再録やグッズ化が行なわれているのだ。
古のデュエル環境を懐かしのカードと共に遊ぶことができる2021年発売のデッキセット「遊戯王OCGデュエルロワイヤル」ではこのカードが再録されつつ、このセットで対戦を行なうルールでは「強欲な壺」を普通に使用する事が許されている。アニメさながらのデュエルを楽しむ事ができ、「早すぎた埋葬」や「ハリケーン」といった古ならではの最強魔法カードも同時に収録されており、新テキストになった実物カードをゲットできるという点でコレクター人気も高い商品だった。
そして壺関連の商品で忘れちゃいけないのが昨年発売された「遊戯王OCGデュエルモンスターズ 壺COLLECTION」だ。
今回取り上げた壺連中を含んだ数多の「壺」カード達が手のひらサイズのフィギュアとなって立体化された商品で、オマケのプロモカードとして「強欲な壺」のクォーターセンチュリーシークレットレア+フィギュア化された壺カードのウルトラレアパラレル仕様が同梱された事で話題を呼んだ。禁止カードを最高レアリティで再録する斬新さに思わず笑った記憶がある。とはいえフィギュアの完成度も高く、再録が無さそうな壺カードたちを高いレアリティでゲットできる二度とないチャンスだったため多くのデュエリストが購入したに違いない。
という訳では今回は足早ながら「強欲な壺」について振り返ってみた。絶対に禁止解除されて帰ってくることは無いとわかっていながらも、どうにも愛せずにはいられない……そんな元祖壺の魅力を共有できていたら嬉しい。
デュエリストである限りこれからも何かしらの「壺」にはお世話になるだろうし、特殊なレギュレーションであればオリジナルの壺でアニメ張りのドローを楽しめるので、今後とも良き関係を保って行きたいところだ。
こんな感じで今後も(色んな意味で)ヤバすぎるカードの紹介記事を書いていく予定なので、その時はチェックしてくれると嬉しい!それではグッッッッ爆アドォォォ!!!
(C)スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
(C)Konami Digital Entertainment








![マックスファクトリー[Max Factory] 西村式デッサン人形 オリーブさん GRAY ノンスケール プラスチック製 可動フィギュア 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41GBsBlkKmL._SL160_.jpg)
![マックスファクトリー[Max Factory] 西村式デッサン人形 オリーブさん FLESH ノンスケール プラスチック製 可動フィギュア 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/412NJ1-xHhL._SL160_.jpg)





![グッドスマイルカンパニー[GOOD SMILE COMPANY] figma リンク ティアーズ オブ ザ キングダムver. DXエディション 再販 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/410qNIh9XkL._SL160_.jpg)







![グッドスマイルカンパニー[GOOD SMILE COMPANY] PLAMATEA 如月ハニー 組み立て式プラモデル ノンスケール 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/416Sue5uTYL._SL160_.jpg)





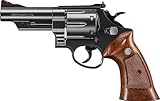


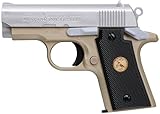







![ゴッドハンド(GodHand) 神ヤス! 10mm厚 3種類セットB [#600/#800/#1000] GH-KS10-A3B 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/41SoT5eE7fL._SL160_.jpg)


![武藤商事(Muto Syouji) MUTOSYOUJI [] プラリペア ブラック PL16B【HTRC3】 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51Hn79+nVuL._SL160_.jpg)














![タカラトミー ポケットモンスター ポケモン30周年記念 モンコレ旅立ちの3匹セット アローラ地方 アローラ地方 ポケモン30THモンコレ3ヒキセツトアロ-ラ [ポケモン30THモンコレ3ヒキセツトアロ-ラ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/edion/cabinet/goods/ll/img_541/4904810098676_1.jpg?_ex=128x128)

![ねんどろいど 勝利の女神:NIKKE アリス[グッドスマイルアーツ上海]【送料無料】《08月予約》 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/amiami/cabinet/pb/2026/052/figure-197769.jpg?_ex=128x128)
![【メガハウス】デスクトップリアルマッコイ ドラゴンボールZ 孫悟空 01 -限定復刻仕様版-【2026年6月発売】[グッズ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/neowing-r/cabinet/item_img_2176/neogds-964760.jpg?_ex=128x128)



![POP UP PARADE ペルソナ5 ザ・ロイヤル ジョーカー L size 完成品フィギュア[グッドスマイルカンパニー]【送料無料】《08月予約》 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/amiami/cabinet/images/2026/082/figure-198780.jpg?_ex=128x128)
![POP UP PARADE NEEDY GIRL OVERDOSE あめちゃん L size 完成品フィギュア[グッドスマイルカンパニー]【送料無料】《発売済・在庫品》 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/amiami/cabinet/images/2025/401/figure-192118.jpg?_ex=128x128)






![GLOCK-106(BK) GLK-106(BK) 【マルイG17/G18C/G26対応】GUARDER エクステンデッド マガジンベース GLOCK◆リアル形状リアル刻印入り[全国一律300円配送可能] 製品画像:20位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/military-base/cabinet/a/item5/glock-106bk.jpg?_ex=128x128)

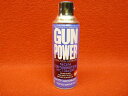




 製品画像:11位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/hobby-online/cabinet/_rc/pandora_rc/4573112279603-1.jpg?_ex=128x128)
 製品画像:10位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/hobby-online/cabinet/_rc/pandora_rc/4560452089047-1.jpg?_ex=128x128)




