特集
激しくぶつかるコマの戦い、奥深いカスタマイズ! 「BEYBLADE X」入門【春特集】
子供も大人も熱くなれる"ギアスポーツ"に参戦してみよう!
2025年3月27日 00:00
1999年から商品展開している「BEYBLADE(ベイブレード)」。現在30歳前後の人たちにとっては子供の頃に馴染みのある玩具の1つだったのではないだろうか?「ベイブレード」は端的に言ってしまえば日本の伝統玩具の1つである「ベーゴマ」をリブートした玩具で、最大の特徴は従来のベーゴマにおける紐を「シューター(ランチャー)」と呼ばれるアイテムを使う事で、誰でも簡単にコマを回せるようにしたところだろう。他にもコマ自体が複数のパーツで構成されており、これらを交換するカスタマイズが行なえる点も従来のコマと異なるユニークなアイディアと言える。
2008年からはメタルパーツを採用した第2世代の「メタルファイト ベイブレード」、2015年からはバトル時に当たりようによってはコマがパーツで分解してしまう"バースト"の概念を盛り込んだ第3世代の「ベイブレードバースト」を経て、2023年からは新たに専用スタジアム上でのギミックを活用した「X(エクストリーム)ダッシュ」が可能となった第4世代の「BEYBLADE X」が登場した。
現在、この「BEYBLADE X」が全国的にかなり盛り上がりを見せている。前述のように最初の「ベイブレード」が登場してから25年が経過し、子供の頃に「ベイブレード」に触れた世代が親になることで、理解のある両親が多くなっている事に加えて、その奥の深さから、子供のみならず、両親も一緒になって遊べる玩具、という点も注目ポイントの1つだ。
こうした状況を踏まえて、タカラトミーでは単なる子供向けの玩具ではなく「ギアスポーツ」と呼んでスポーツの一環として盛り上げていこうという意向もあるようだ。筆者も実際に大会の取材で興味を持ち、1度手を出したが最後、ずっぽりとハマる事になった。その後、様々なベイを購入して、現在では日々Webサイトで最新ベイの情報収集や、カスタムに関する動画や情報を収集しては試行錯誤の日々を過ごしている。
そこで今回は改めて「BEYBLADE X」とはどのような玩具か、という基本的な解説を行なうことで、改めてベイブレード初心者の筆者自身も理解を深めていくとともに、より多くの人に「BEYBLADE X」の魅力を知ってもらい、一緒に遊んだりバトルしてもらいたい。
3つのパーツカスタムでより強いベイを構築
「BEYBLADE X」は、自分でカスタマイズしたコマ(以降、ベイ)を使用し、専用スタジアム上にて対戦を行なう「ギアスポーツ」だ。対戦は1対1で行なわれ、試合開始時には「3・2・1、ゴーシュート!」の掛け声と同時にベイを回して、ぶつけ合い、最終的にスタジアム上で回転を続けたベイが勝利となる。
ベイの構造は「ブレード」、「ラチェット」、「ビット」の3パーツで構成されており、それぞれのパーツには、攻撃特化の「アタック」や防御特化の「ディフェンス」、より長く回り続ける「スタミナ」、これら3つの属性を複数持つ「バランス」などのタイプが設定されており、これらパーツの組み合わせで、より強いベイを構築して対戦に挑む。それぞれの相性として、アタックはスタミナに強く、スタミナはディフェンスに強く、ディフェンスはアタックに強く、と三すくみになっているほか、どのタイプとも戦えるという立ち位置のバランスタイプがある。
ここで「ランチャー」についても触れておこう。ベイを回すためのアイテム「ランチャー」には主に回転部に直結した紐を引っ張って回転させる「ストリングランチャー」と、凹凸が刻まれた軟性プラスチック製のワインダーと呼ばれる棒を引き抜いて回転させる「ワインダーランチャー」がある。
「BEYBLADE X」の製品群は主に「スターター」と「ブースター」があり、前述のランチャーが付属するのが「スターター」、ベイのみで販売されているのが「ブースター」となる。
製品名にも意味があり、「BX」は「ベーシックライン」、「UX」は「ユニークライン」、3月29日から新たに登場する「CX」は「カスタムライン」と呼び、ベーシックラインはランチャーに装着するランチャーフックがメタル製のベーシックな製品を意味し、ユニークラインは樹脂製のランチャーフックを備え、製品ごとに固有の性能を持った文字通りユニーク(個性的)な製品となっている。
新たに加わるカスタムラインはこれまで単体だったブレードがさらに「ロックチップ」、「メインブレード」、「アシストブレード」の3パーツに分解可能となり、ブレードその物がカスタマイズ可能になった製品だ。
商品としては、これら3つのパーツが組み合わさった状態で販売されているので、既にランチャーを持っている人ならどれでも、初めて購入する場合はランチャーの付属する「スターター」を購入すれば、買ってからすぐにベイを回す事ができる。
なお、別売オプションとして、装着する事で、スマートフォン用の「BEYBLADE X」専用アプリと連動して、シュート時のパワーなどを計測できる「ベイバトルパス」も用意される。また、ランチャーに装着して持ちやすさを向上する「カスタムグリップ」もある。
奥が深すぎるベイのカスタマイズ!
カスタマイズについては「ブレード」、「ラチェット」、「ビット」の3つのパーツがあるが、これら全てのパーツが非常に重要な要素となっており、どれか1つだけが強くてもベイの「コマ」としての総合力が高くなるとは限らないのが面白いところだ。
ブレードはベイそのままを現すパーツと言える。「ウィザードロッド」、「ドランバスター」、「ワイルドウルフ」といった名前があり、ブレードの形、重さなどで特性が異なる。このブレードの特性をより活かすために、ラチェットやビットを付け替えていくのである。
例えば、4月から殿堂入りが決まっている「UX-03 ウィザードロッド5-70DB」は、購入したままの組み合わせで使っても実はあまり強くならない。製品名には全てのパーツ情報が含まれており、ウィザードロッドの場合は、ラチェットが「5-70」、ビットは「DB(ディスクボール)」が標準で装着されているのだが、ブレード以外のパーツを実際に使ってみると、ウィザードロッドとあまり相性がよくないからだ。
ラチェットの「5-70」は他のコマと接触しやすい5枚刃を含み、高さが70のパーツだ。そしてビットの「DB(ディスクボール)」は円盤状の重りが付いた接地面が球状のパーツとなる。
ラチェットには現在60~85までの高さのパーツが用意されており、重心を下げたい場合はより低いパーツを、上から叩きつけるような攻撃を決めたい場合には高いパーツを使用する傾向にあるようだ。一方で高すぎると、安定性が大きく低下してしまうため、実際には60~70が広く使われているのが現状だ。
ラチェットの刃の数はブレードとの関連性も重要で、例えばアタックタイプの「UX-01 ドランバスター1-60A」の場合、ブレード自体に攻撃性能が高そうな大型の攻撃刃を備えるので、この攻撃刃と同じ向きに装着できる1枚刃のラチェット「1-60」を備える事で攻撃力を更に高める、といった役割を持たせる。
「ウィザードロッド」に備える5-70は、安定性重視の「ウィザードロッド」にとっては高さがありすぎるため、多くのブレーダーたちは、より低い高さの60のラチェットを選ぶ傾向にあるようだ。
ビットはさらに難解だ。先端部の違いや、軸に備えるギア歯の違いなどから、多種多様な動きを生み出せるようになっているが、例えば安定した回転を保持するなら「B(ボール)」、わざと不安定な動きにさせるなら「Q(クェイク)」、X(エクストリーム)ダッシュの性能を高めるために、大型ギアを持たせた「A(アクセル)」など、選択の幅がかなり広い。
DBは一見すると強そうなパーツに見えるのだが、実際に組んでみると、ラチェットと円盤状の重りの間に隙間が生まれてしまい、バースト(分解)しやすくなっているようで、実際に何度かバトルさせてみると、かなりの高確率でバーストしてしまった。
そのため、安定性の高さが特徴のブレード「ウィザードロッド」をさらに安定して使うために、多くのブレーダーたちは「B(ボール)」や「FB(フリーボール)」といった、安定性重視のビットにカスタムしてバトルで使用することで、多くの実績を上げる事となった。
このように、安定したブレードに対して、さらに安定性を高めるパーツをチョイスするか、あえて攻撃的なパーツをチョイスする意外性を見せるかなど、パーツごとの組み合わせや相性を、全国のブレーダー各自が検証したり調査して、最適解を求めているというわけだ。あまりの奥の深さから調べれば調べるほど、深い沼に陥るような感覚を覚えるが、この沼の感覚こそ、「BEYBLADE X」が人気の秘密の一端であると感じられる。
誰でも参加可能な大会も全国各地で開催
実際のバトルについては、「BEYBLADE X」専用のスタジアムで行なう。スタジアムは周辺部が透明のカバーで覆われており、ベイが外に飛び出さないような構造で、上部に空けられたスペースからベイをシュートしてバトルを行なう。スタジアムの内部には、外周部にギア歯の枠が組み込まれており、ここにベイのビットに備えるギアが噛み合うことで、超高速加速「X(エクストリーム)ダッシュ」が発動するようになっている。これにより、通常のベーゴマなどでは発生し得ない、強力な攻撃が発動するという仕組みだ。
勝敗については4ポイント先取で、ポイントは、自身のベイがより長く回っていた場合は「スピンフィニッシュ」として1ポイント、対戦中に相手のベイを分解させた場合は「バーストフィニッシュ」で2ポイント、「BEYBLADE X」専用スタジアムは、上部に3つのポケットが用意されており、両端のポケットに相手のベイを弾き飛ばした場合は「オーバーフィニッシュ」で2ポイント、中央のエリアに弾き飛ばした場合は「エクストリームフィニッシュ」として3ポイントが獲得できる。
なお、バトルには「シングル」と「3on3」があり、シングルの場合は同じベイを使用するが、「3on3」では3種類のベイを用意し、専用ケースに入れて、それぞれ出してバトルする。他にも3人同時にバトルする「3人バトル」や「チーム戦」などのルールも用意されている。
こうしたバトルはスタジアムを購入する事で、自宅などでも遊べるほか、フリー対戦台を備えるおもちゃ屋や施設などでも遊べる。また、公式大会も定期的に開催されており、オープンクラスの大会であれば誰でも自由に参加が可能だ。なお、大会のレギュレーションには6~12歳の年齢制限がある「レギュラークラス」も用意されている。
参加するには、BEYBLADE Xの公式ホームページからストア情報を検索、最寄りの店舗情報やイベント情報をチェックして申し込みを行なう。
今回、筆者の住む神奈川県の大会情報を公式ホームページでチェックしてみたが、各地の大会情報が簡単にチェックできて非常に使いやすい。こうして大会情報を眺めてみると、アクセスしやすい家電量販店で開催される大会の多くは、定員数が少なくて事前抽選だったり、当日店舗での抽選が行なわれたりなど、参加する事自体がかなり狭き門となっている大会も多く見られた。この辺りは実際に店舗に顔を出して、店員などと直接会話して情報を得るのがよさそうだ。
コレクション要素も楽しい
「BEYBLADE X」のベイを実際に購入してみると、そもそも分解したり、再構築したりといった組立作業がとても楽しい。当初は2つのベイを購入していたが、2種類のブレード、ラチェット、ビットをあれこれと組み替えるだけで気持ちが高まる。
ベイブレードの中央部にはそのベイを象徴するアイコンの図柄が描かれているのだが、これもセンスがよい。例えば「ウィザードロッド」であれば、魔法使いのアイコンが描かれているし、「フェニックスウィング」なら赤色の不死鳥が描かれており、どれもイメージにピッタリのデザインとなっている。
そして本格的にカスタムしようとすると、ブレードは元より、ラチェットやビットも色々とほしくなってくる。スペック情報などをチェックして「このビットは強いんじゃないか?」、「このラチェットなら安定しそうだ」、「このブレードは評判がいいな」など、あれこれ検討した上で気になるブレード、ラチェット、ビットを含むベイを購入する。そうこうしているうちに僅か1か月くらいの間に、筆者の手元には19個のベイが集結することとなった。
加えて、先日の発表で、マーベルヒーローやスターウォーズ、トランスフォーマーとのコラボモデルが日本国内でも発売されることが明らかになった。実は筆者はトランスフォーマーのコラボベイを直輸入にて購入した事があるのだが、これらが正式に日本でも流通するのはなかなかの衝撃だ。ぶっちゃけコラボモデルは、中央部のアイコンの図柄もカッコいいが、ブレード全体のデザインもコラボの内容を意識した物になるなど、かなり凝った作りとなっているので、機会があれば手に入れてみてほしい。
日々の自主トレやアプリ連動機能なら1人でも楽しめる
このようにコレクションアイテムとして見ても楽しい「BEYBLADE X」だが、一方で最大の課題は実際にベイを使って遊ぶには、実際に対戦することこそが本当に楽しいということだ。ただし「BEYBLADE X」においては、対戦ができなくても、1人で楽しめる要素も用意されている。
何はともあれ先ずはスタジアムを購入するところから始めたい。もちろん単にシュートしてベイを回すだけならどこでもできるが、ランチャーで回転させる「BEYBLADE X」の場合、その回転力はかなり高い上にブレードにメタル素材を採用するベイを何もない場所で回すと、壁に当ててしまったり、家具に衝突して傷をつけてしまう危険性が高い。
加えてスタジアム以外の場所でベイを回すと、ベイのブレードやビットに傷がついてしまう。状態の悪いブレードやビットなどのパーツは、大会などの事前チェックで弾かれてしまい、使えなくなってしまう場合もあるので、可能な限りスタジアムを用意するのがいいだろう。
さらには実際にバトルする際のシュートは真下に落とすだけではなく、角度を変えてシュートするなど、色々なテクニックがあり、こうした様々なシュートスタイルを練習するのにスタジアムが必要不可欠なのだ。
シュート練習するような場合に役に立つのが、「ベイバトルパス」によるシュートパワーの測定だ。ベイバトルパスは電池駆動のオプションパーツで、使用するランチャーに装着することで、シュートパワーを測定できる。単体では測定しか行なえず、実際の数値の確認には「BEYBLADE X」アプリをインストールしたスマートフォンと連携して使用する。複数回シュートした場合、その測定結果はまとめて同期されるので、同期後にこれまでの履歴を確認したい場合は、「メニュー」の「シュート情報」を確認する事で、直近のシュートデータとして、50回分までは追うことができる。また、シュート測定の回数に応じてポイントが獲得できる。
アプリ上には「シュートジム」というメニューもあり、仮想的なスタジアムでベイバトルが行なえる仕組みも用意されており、ここでは「ベイバトルパス」を装着したランチャーでベイを実際に回す事で、アプリ内のスタジアムでバトルが行なえる遊び方も用意されている。ここでもシュートパワーが確認できるので、1回毎にシュートパワーを確認したい場合は、こちらを活用するのも有効だ。また、この仮想スタジアムのペイバトルで勝利した場合もポイントが貰える。
このように「BEYBLADE X」アプリでは、測定結果の履歴などが確認できるほか、購入したベイの登録などが行なえる。ベイを登録した場合もかなり多くのポイントが獲得できる。
こうして貯まったポイントを使う事で、アプリに備える「RARE BEY GET BATTLE」と呼ばれるミニゲームがプレイでき、抽選でアプリ限定のベイが貰えたり、購入できるという特典も用意されている。このポイントは、前述のような大会の参加賞としても活用されており、参加するだけで、ポイントが獲得出来たりもするほか、「BEYBLADE X」を取り扱う店舗などに来店することでもポイントが貰える仕組みも用意されている。
対人戦のバトルこそが「BEYBLADE X」の魅力なのは間違いないが、なかなか都合がつかなかったり、対戦場などに行く機会がない場合も、このように1人で遊べるような仕組みが色々と用意されているのだ。
コレクションもシュートも楽しい「BEYBLADE X」
以上、「BEYBLADE X」の初歩的な情報を中心にまとめてみた。リリースから2年が経過しつつある「BEYBLADE X」だが、間もなく登場する「CX(カスタムライン)」など、新たな挑戦的な商品も続々と登場するなど、遊び甲斐のある玩具であることは間違いない。
「BEYBLADE X」はアナログなベーゴマがベースのため、デジタル的な机上の空論や理屈が通じないのが面白いところだ。初めての大会出場の際にも感じたことだが、重量だったり、直径だったりといった数値データは自分で調べてもいいし、インターネット上にそうしたデータをまとめたWebサイトなども多く存在しているが、こうしたデータを元に構築したベイが実践では全く歯が立たないのが面白いところでもあり、難しい部分でもある。「ギアスポーツ」と同社が呼ぶように、「BEYBLADE X」ではシュートの精度やタイミングが毎回異なる点も重要な要素の1つなので、こうした技術の向上については従来のスポーツのように日々の鍛錬が物をいう点も重要なポイントと言えそうだ。
少なくとも大会などで、1度は結果を出してみたい。そんな思いで引き続き筆者は「BEYBLADE X」を追いかけていく。興味がある人は是非1度、おもちゃ屋や家電量販店などのおもちゃコーナーの一角にある「BEYBLADE X」のスペースを覗いてみてはいかがだろうか?

















































![マックスファクトリー[Max Factory] 西村式デッサン人形 オリーブさん GRAY ノンスケール プラスチック製 可動フィギュア 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41GBsBlkKmL._SL160_.jpg)
![マックスファクトリー[Max Factory] 西村式デッサン人形 オリーブさん FLESH ノンスケール プラスチック製 可動フィギュア 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/412NJ1-xHhL._SL160_.jpg)





![グッドスマイルカンパニー[GOOD SMILE COMPANY] figma リンク ティアーズ オブ ザ キングダムver. DXエディション 再販 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/410qNIh9XkL._SL160_.jpg)







![グッドスマイルカンパニー[GOOD SMILE COMPANY] PLAMATEA 如月ハニー 組み立て式プラモデル ノンスケール 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/416Sue5uTYL._SL160_.jpg)





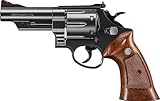


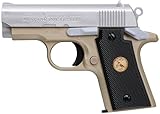







![ゴッドハンド(GodHand) 神ヤス! 10mm厚 3種類セットB [#600/#800/#1000] GH-KS10-A3B 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/41SoT5eE7fL._SL160_.jpg)


![武藤商事(Muto Syouji) MUTOSYOUJI [] プラリペア ブラック PL16B【HTRC3】 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51Hn79+nVuL._SL160_.jpg)



![バンダイスピリッツ ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2 ガンダム EGEX1RX-78-2ガンダム [EGEX1RX782ガンダム] 製品画像:18位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/edion/cabinet/goods/ll/img_228/4573102607478_ll.jpg?_ex=128x128)


![バンダイスピリッツ HG 1/144 ガンダムエアリアル GWHG03ガンダムエアリアル [GWHG03ガンダムエアリアル] 製品画像:15位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/edion/cabinet/goods/ll/img_263/4573102630308_ll.jpg?_ex=128x128)


![ビークルモデル トレンチランセット [STAR WARS: A NEW HOPE] (プラモデル) 製品画像:12位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7806/4573102697806.jpg?_ex=128x128)
![ビークルモデル レイザー・クレスト [STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU] (プラモデル) 製品画像:11位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8971/4573102698971.jpg?_ex=128x128)
![【中古】[PTM] (再販) HG 1/144 ゲルググ ボカタ機(GQ) 機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ガンダム ジークアクス) プラモデル(5068590) バンダイスピリッツ(20260221) 製品画像:10位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/6313/4/cg63134465.jpg?_ex=128x128)
![【中古】[PTM] (再販) HG 1/144 シャア専用ザク(GQ) 機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ガンダム ジークアクス) プラモデル(5069190) バンダイスピリッツ(20260124) 製品画像:9位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/6313/4/cg63134659.jpg?_ex=128x128)





![トイ・ストーリー4 リアルサイズトーキングフィギュア ジェシー[タカラトミー]《発売済・在庫品》 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/amiami/cabinet/images/2022/45/figure-146855.jpg?_ex=128x128)

![タカラトミー 冒険大陸 アニアキングダム キングゴールドマウンテン アニアKDキングゴ-ルドマウンテン [アニアKDキングゴ-ルドマウンテン] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/edion/cabinet/goods/ll/img_371/4904810955818_1.jpg?_ex=128x128)


![カネキャップ(8連×12リング)×4箱 《384発分》 トイガン用[ゆうパケット発送、送料無料、代引不可] 製品画像:18位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/vaps2shop/cabinet/image44/4580566392178_1.jpg?_ex=128x128)




![【14mm逆ネジアウターバレル対応/逆ネジ→正ネジの変換に】G&P 1インチ アウターバレル エクステンション CCW/CW/BK◆延長パーツ/レングス調整[全国一律300円配送可能] 製品画像:13位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/military-base/cabinet/a/item13/gp-brl063s.jpg?_ex=128x128)




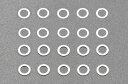
![TKSK TK-147 RC配膳ロボットプチ TK147RCハイゼンロボツトプチ [TK147RCハイゼンロボツトプチ] 製品画像:11位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/edion/cabinet/goods/ll/img_355/4589648021470_1.jpg?_ex=128x128)
 製品画像:10位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/hobby-online/cabinet/_rc/topline-5/4589434364712-1.jpg?_ex=128x128)
 製品画像:9位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/hobby-online/cabinet/_rc/hrd_project/4595057001057-1.jpg?_ex=128x128)





