組立開始。待望の新型MGゼータガンダムの超絶設計をかみしめる
まずは頭部から組んでいきます。先ほどのランナー紹介のところで“おや?”となった方もいらっしゃると思いますが、なんとアンテナが2セットあるように見えますね。特に予備用と明言はされていないのですが、一つは可動用、一つは固定用とされています。
ただ、メインアンテナのパーツ番号は同じなので予備と捉えることができます。ゼータは可変機ということもあり、アンテナを破損してしまう場合もあると思いますのでこれはウレシイ配慮ではないかと思いました。予備パーツとして保管することをオススメします。
頭部の構造は特に難しいところはありませんが、内部からクリアーパーツを挿入してのツインアイを表現したり、エクストラフィニッシュのパーツを用いた左右のバルカン砲の砲口が小さいパーツになりますので飛ばさないように注意しましょう。
メインアンテナは同じパーツ(K8/K9)が2セット。これはうれしい! 赤いアンテナ基部は可動(右)と固定(左)の2つ。“Z”の刻印も見えます 頭部本体はコアとなるフレームに前後左右の装甲パーツを組み付けます コアパーツ裏からツインアイのクリアーパーツを組み込みます とても細かいバルカン砲はエクストラフィニッシュです 側頭部を組付けました。バルカン砲とダクトなどが強調されます 首とボディとの接続部は複雑に見えますが構造自体は簡単です。耳には別パーツ化されたカバーがあります アンテナを組み付けます。今回はもちろん可動アンテナで! 余剰パーツは保管しておきましょう。そしてダカールでアッシマーを助けられそうな首の角度! 全て組み上がってこれができたら最高です。 上半身を組み立てる。さらに極まった可変と可動機構に驚く
変形機構を持つゼータガンダムのガンプラでは、可変機構をいかに盛り込んでくるのか? をテーマに、そのベースとなる胴体は毎回組んで進化を実感するのが楽しい部位となります。今回“Ver.Ka”版では、可変機構は当たり前に存在したうえでさらに可動機構を高次元で融合させることに成功しています。
主な拡張性能としては肩部の回転機構でこれによって腕部全体を上方に跳ね上げられるようになりました。驚くべき機構ですが、組んでみると“なるほど!”、よくよく考えると“なんでこれを思いつくんだ!”と設計と素材と成型技術の進化はこういう結果を生むのかと驚くばかりです。さらに変形機構も極まっていて装甲部の複雑な可動を実現しています。組み上がって変形させたらどのように作用するかが楽しみになります。
ボディパーツ一覧。変形機構のため、細かくパーツ分けされています 腹部左右(脇腹)で開閉するフレームを芯フレームに組み込みます 背中のフレームに肩とフライング・アーマーの接続フレームを組付けます 背中側に軸が用意されて、そこへ回転できるパーツを組み込むことで新しい可動性能を獲得しました 背中フレームの下向きに伸びている軸がフライング・アーマーの接続軸です 左のパーツはテール・スタビライザーの接続部であるとともにフライング・アーマーの軸を固定します 中央にはテール・スタビライザーを固定するためのツメを装備します コクピットブロックはリニアシートの回転機構も持っています 今回カミーユ君は事情により乗っていませんが製品版では搭乗します コクピットブロックはボールジョイントで接続、ポージングの際に微妙な角度を付けられます 黄色いダクトを組付ければ一気にガンダムタイプのイメージに 胸部装甲、首のところにはディテールパーツを付けます “Ver.Ka”シリーズでアイコンになっている胸部の4本のアンテナ状パーツはエクストラフィニッシュされています 胸部を裏から見るとツメが見えるので、そこに組み込みます 実は黄色いえりのパーツがここまでばっちり見える可変モデルのゼータガンダムは多くありません。筆者にとっても不満な点でもありましたがついに解決されました1 肩関節も結構動きます。腕部本体を取り付けたらどこまでいけるか楽しみです テール・スタビライザー本体は上下から、基部は左右から挟み込む構造です 内部にノズル状パーツを入れ込み、フレームを内包します ボディ本体とがっちり組まれることで外れることはありません 折りたたまれたテール・スタビライザーは固定用ツメで…… 腕部を組み立てる。一歩ずつ設定に近づくゼータのガンプラ!
腕部は変形に対応するため細くなりがちでしたが、非変形モデルを彷彿とさせる太さを獲得している印象です。末端にあるハンドパーツもだいぶ大きいのがそう思わせる一因にもなっているようです。ゼータガンダムのアニメーション設定をよく見ると意外と太めだということも再確認でき、今回そのイメージを具現化したものとなっています。
外側へ張り出す肩の上部にあるバーニアをどのように収納するか。ウェイブ・ライダー時に機体をなるべく薄くしたいため、ここもこれまでのガンプラでの挑戦が続く難所となっています。過去のガンプラでは装甲内側に収納するというアプローチでしたが、ということは内部がスカスカ……ということにもつながり説得力という意味では合理的ではなかったように思います。
“Ver.Ka”では肩部バーニアを“へ”の時に折り曲げることで張り出しを抑えることができています。さらに、肘関節が前腕に収納される機構も盛り込まれました。実はこれ、ゼータガンダムのアニメーション用設定にあったもの(実際にはもっと縮みます)ですね。ついにこの設定まで盛り込まれたことになります!
MGシリーズならではのフレームと装甲の構成、複雑に見えますが挟み込み構造が多いのでむずしくはありません フレーム本体に黄色のディテールパーツを組み込んで…… 上腕+肘関節とグレネード・ランチャー+接続ラッチを入れ込みます 左右から装甲でグレネード・ランチャーハッチと腕内側のパイプ状パーツを挟み込みます パイプ状パーツには腕の伸縮時のロック機構の役目があります 肩部を組み立てます。変形機構があるので多めのパーツ量になりますね 上部バーニアはフレームに黄色のディテールパーツを組み入れて青い装甲でカバーします 腕部で大変なのは肩アーマー前後にあるバーニアかもしれません 黄色のノズルパーツがとても小さく、さらに押し込むのではなく上からはめ込む構造のせいもあり外れやすい印象です 今回のサンプルでは、ここは接着したほうが作業効率が格段に上がります ハンドパーツはとても大きく、設定画を彷彿とさせます。現段階では握りこぶしと平手を組みます 親指の付け根が白いのも往年のファンとしてはうれしい限り ウェイブ・ライダーへの変形時は握りこぶしを使います 肩部が回転することで思いっきり派手なアクションもとれそうです ぐいっと曲がった肘と大きい握りこぶしで力強さを感じさせます 肘関節にも前後へのスイング機構があります。そして腕の伸縮機構でとても印象が変わります 腰部を組み立てる。凝縮された変形機構とロック機構!
ゼータガンダムの腰部は実はとんでもない変形機構を有している部位になります。ウェイブ・ライダー時には両脚は外側へ移動することになりますのでそこをどう実現するか、これまでのガンプラでも多様にチャレンジが繰り返されてきた部分です。
“Ver.Ka”ではその変形機構を実現するために複雑な構造にするのではなく、一つ一つのパーツをシンプルで大きくすることで剛性を上げることができているようです。そして可動する部分が外れにくい構造だったり、ロックする機構を持たせてあってモビルスーツ、ウェイブ・ライダー両形態を高次元で確立しています。
さらに股関節のロック機構を併せ持つフロントアーマー接続部も組付けます コアフレームが出来上がったら左右の脚部を接続するフレームを組付けます コアフレームのツメ付きの回転軸に組付け……回転させると、簡単には外れない構造になっています 左右をおろして、フロントアーマーフレーム(写真右側)で…… 上段がフロント、下段がリア。それぞれにディテールやバーニアが内包されます 左がフロント、右がリア。それぞれの裏側もディテールが楽しい フロント中央にはウェイブ・ライダー時にランディング・ギアになる機構が盛り込まれています 









![マックスファクトリー[Max Factory] ねんどろいどもあ 東方Project ゆっくりしていってね!!! ノンスケール プラスチック製 塗装済みフィギュア 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/41PPbgmtMTL._SL160_.jpg)









![BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ) 30MS SIS-E00 ミャスティ[カラーC] ノンスケール 色分け済みプラモデル 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/416LIRWNpkL._SL160_.jpg)



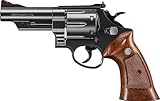


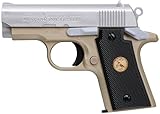








![ゴッドハンド(GodHand) 神ヤス! 10mm厚 3種類セットB [#600/#800/#1000] GH-KS10-A3B 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41SoT5eE7fL._SL160_.jpg)

![武藤商事(Muto Syouji) MUTOSYOUJI [] プラリペア ブラック PL16B【HTRC3】 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51Hn79+nVuL._SL160_.jpg)











![バンダイスピリッツ Figure-rise Standard ウルトラマンティガ マルチタイプ FRSウルトラマンテイガマルチタイプ [FRSウルトラマンテイガマルチタイプ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/edion/cabinet/goods/ll/img_302/4573102674210_ll.jpg?_ex=128x128)





![【中古】[FIG] アーチャー/アルトリア・ペンドラゴン【Summer Queens】 Fate/Grand Order(フェイト/グランドオーダー) 1/8 完成品 フィギュア あみあみ&でじたみん&東京限定 アワートレジャー/東京フィギュア(20210531) 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/6123/3/cg61233210.jpg?_ex=128x128)
























