特別企画
杉山淳一の「鉄道ジオラマ旅情」、第4回:山梨県都留市「山梨県立リニア見学センター どきどきリニア館」 猛スピードで走るリニア、どうやって動かしている?
2020年12月7日 05:15
今回の旅:「山梨県立リニア見学センター どきどきリニア館」
所在地: 山梨県都留市小形山2381
開館時間:9:00~17:00(入館は16:30まで)
休館日:毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌火曜日) 12月6日(日)までは毎日開館
入館料:一般・大学生420円 高校生 310円 小中学生 200円 就学前児童 無料
アクセス:JR中央線大月駅よりリニア見学センター行路線バスで15分
10月19日、JR東海はリニアモーターカー(以下、リニア)中央新幹線山梨実験線で「L0系」改良型車両の報道機関向け試乗会を開催した。この日は隣接する有料見学施設「どきどきリニア館」も報道関係者に無料公開されていた。JR東海としては、試乗・撮影だけではなく、もっとリニア中央新幹線の知識を深めてほしいという意図があっただろう。「どきどきリニア館」にとっても、PRの機会だ。そして報道関係者も展望フロアから走行写真を撮影できる。三方良しだ。
「どきどきリニア館」の3階に展望フロアがあり、同じフロアに大きなジオラマがあった。全長約17m、最大奥行きは約8メートル。テーマは「リニア中央新幹線開業後の山梨県」だ。中央の高架をリニア新幹線が走り抜け、地上は中央本線、身延線、富士急行の電車が走る。風景は山梨県の名所を散りばめ、約12分の展示運転で各所にスポットライトを当てて紹介する。もっと簡素なジオラマを予想していたら本格的だ。この日は閉館間際の訪問だったため、後日あらためて取材させていただいた。
リニア中央新幹線山梨実験線はJR東海の施設だ。この実験線はそのままリニア中央新幹線の本線になる。実験線に隣接して、「山梨県立リニア見学センター」がある。こちらは山梨県の施設で「わくわくやまなし館」、「どきどきリニア館」の2棟で構成されている。「わくわくやまなし館」は1996年に建てられ入場無料。ミュージアムショップ、観光情報センター、屋内展望室がある。「どきどきリニア館」は2014年に新館として建てられ、上記の通り入館料が必要。1階に2003年に最高速度581km/hを記録した試験車両(MLX01-2)の実物を展示するなど、リニアに関する博物館となっている。
公共交通機関の交通アクセスは、JR中央本線大月駅から富士急バスの「県立リニア見学センター行き」がおおむね1時間に1本程度、所要時間は15分。大月駅から富士急行の電車に乗り、禾生駅から徒歩13分。ただし道のりは丘越えになるので、ハイキング感覚で。大月駅からバスをオススメする。
無料駐車場が広いので、ドライブの目的地としてもオススメだ。少し離れた笛吹市の「リニアの見える丘」、「花鳥山展望台」にも行ってみよう。ここは実験線の地上区間で、走行風景がよく見える。2020年11月現在、「花鳥山展望台」からは新しい改良型試験車の先頭車、「リニアの見える丘」からは初代L0系の先頭車を観られる。なお、試験走行の有無はJR東海の公式サイトで確認しておこう。
午前中は笛吹市、午後は都留市の山梨県立リニア見学センターへ。飲食施設はないけれど、見学センターのそばに「道の駅つる」があるので、ランチタイムはここで。リニアを満喫する日帰りドライブを楽しんでほしい。
【著者近況】
11月は大井川鐵道満喫ツアーに参加、アプト式機関車研修庫で作業ピットに潜り、車両側の歯車を間近に見られて感激。この歯車とレール側のギザギザを噛み合わせて急勾配を登る仕組み。今回の取材の山梨県ドライブも好天に恵まれ楽しかった。乗り鉄だどクルマも好き
風景重視のジオラマを、猛スピードでリニアが通り抜ける
「どきどきリニア館」のジオラマも「風景重視型」で線路配置はシンプルだ。中央本線の複線の線路が大きく周回し、左手に大月駅、右手に甲府駅を再現している。大月駅から富士急行線の電車が発着して、リニアの線路を潜って山の裏手に回る。そこには富士急ハイランドや山中湖がある。甲府駅からは身延線の線路があり、こちらもリニアの線路を潜って奥へ。そこには身延山久遠寺があり、ロープウェイも見える。
実はこのほかに小海線のディーゼルカーも走っているけれど、線路が短くてわかりにくい。毎時10分、30分、50分に約8分間の演出運転があり、その序盤にひょっこり顔を出す。右手の山の牧場の上、注意深く探してみよう。
リニア中央新幹線はジオラマの中央部で一直線に貫いている。ここは複線で、ものすごい速さですれ違い、ときどき中央に構えた「山梨県駅」に停車する。大月駅寄りにはJR東海の実験棟と、ここ「山梨県立リニア見学センター」が再現されている。
リニア列車があまりにも速く、リアリティを感じるけれど、この走行は鉄道模型の常識を越えている。いったいどんな仕掛けだろう。まさか本当に磁気浮上式で走行しているのか。そういえば2015年にタカラトミーは磁力で浮上走行する「リニアライナー 超電導リニアL0系スペシャルセット」を発売した。2020年にはノエルコーポレーションがNゲージサイズの磁気浮上式「Nリニア」を発表している。
リニアのような速さを実現している秘密に迫る
さて、このジオラマのリニアの仕掛けはどうなっているか。センター長の大神田氏に聞いた。仕掛けはとても単純で、ワイヤーと磁石を使っている。軌道の表面は滑りやすいアクリル製、リニア車両の底もアクリル製で、鉄の部品を埋め込んでいる。軌道のウラに磁石つきのワイヤーがあって、ワイヤーを高速で巻き取ると車両が滑っていく。
仕掛けとしてはケーブルカーである。ただし、磁石を使っているから、いちおう磁力で動いているというオチかもしれない。ワイヤーの巻取り装置はジオラマの両端にある。
しかし、このケーブルカー方式だと、リニア列車はそれぞれの軌道を行なったり来たり。つまり、右側通行と左側通行の繰り返しになる。それではリアリティに欠ける。
そこで、もう1つ工夫して左側通行に固定してある。列車が両端のワイヤー巻き取り部に到着すると、列車をまるごとスライドさせて、常に左側から発車できるようになっている。実際の鉄道車両工場で車両をスライドさせる「トラバーサー」と同じ仕組みだ。仕組みは単純だけど仕掛けは大がかり。このおかげで、リニア新幹線は常に左側通行で走っている。ジオラマで当たり前に見える風景を実現するために、そこまでやるかと感心した。
もうひとつ、中央本線の列車の入れ替わりにも注目だ。複線の外周はスーパーあずさ「E351系」とかいじ「257系」、内周は中央線快速E233系と257系が走る。1つのエンドレスで2列車を走らせ、しかも駅に停車させている。これはジオラマの奥の隠れた場所に待避線を置き、ポイントを切り替えて列車を切り替えている。待避線は山梨県駅の下あたりだろう。耳を澄ませばポイントの作動音が聞こえる。
大神田センター長によると、目下の課題は車両の更新だという。今年、リニア車両は改良型が登場して実験走行が始まっている。中央本線も新型特急車両E353系が登場した。富士急行トーマスランド号も去年引退した車両だ。これはかわいいからそのままでもいいと思うけれど、2018年に新型車による「トーマスランド20周年記念号」がデビューしているし、このジオラマは緑が多いから、真っ赤な富士山ビュー特急も似合いそうだ。
「合同会社丹青やまなし」は丹青社グループの非連結子会社だ。本連載第2回で紹介した敦賀赤レンガ倉庫ジオラマも丹青社だった。風景の作り込みには納得だ。敦賀市は赤レンガジオラマを制作するにあたり、このリニアのジオラマで手応えを感じたのだろう。
ゆったりとした線路配置の中で、風景の作り込みは緻密だ。前述の富士急ハイランドや山中湖のほか、桃畑、川中島合戦、石和温泉、昇仙峡、清里牧場、甲府市役所、米倉山太陽光発電所など50カ所以上のビューポイントを盛り込んだ。演出プログラムでは、自動アナウンスに合わせて、それぞれのポイントにスポットライトを当てつつ、奥の壁に実際の風景を映し出す。列車の走行も含めて、演出はすべてコンピュータで集中管理している。
ジオラマが広いから、各スポットを目線で追い切れない。山の向こうは見えないから、ジオラマの前を左右に走ってみたくなる。それはさすがに大人げないから、2回、3回と分けて見学した。同じフロアに実物のリニア走行を眺められる見学ラウンジがあり、走行実験が始まると館内アナウンスで知らせてくれる。実物のリニアを見て、ジオラマを見て、また実物の走行を見て、ジオラマに戻る。忙しいし、楽しい。





![マックスファクトリー[Max Factory] 西村式デッサン人形 オリーブさん GRAY ノンスケール プラスチック製 可動フィギュア 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41GBsBlkKmL._SL160_.jpg)
![マックスファクトリー[Max Factory] 西村式デッサン人形 オリーブさん FLESH ノンスケール プラスチック製 可動フィギュア 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/412NJ1-xHhL._SL160_.jpg)





![グッドスマイルカンパニー[GOOD SMILE COMPANY] figma リンク ティアーズ オブ ザ キングダムver. DXエディション 再販 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/410qNIh9XkL._SL160_.jpg)





![グッドスマイルカンパニー[GOOD SMILE COMPANY] PLAMATEA 如月ハニー 組み立て式プラモデル ノンスケール 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/416Sue5uTYL._SL160_.jpg)








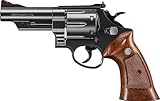




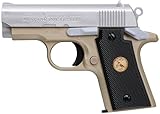





![ゴッドハンド(GodHand) 神ヤス! 10mm厚 3種類セットB [#600/#800/#1000] GH-KS10-A3B 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41SoT5eE7fL._SL160_.jpg)


![武藤商事(Muto Syouji) MUTOSYOUJI [] プラリペア ブラック PL16B【HTRC3】 製品画像:8位](https://m.media-amazon.com/images/I/51Hn79+nVuL._SL160_.jpg)












![【2025年8月16日発売】【新品】ホルス・ヘレシー: エイジ・オヴ・ダークネス・ダイスセット [ウォーハンマー40,000] [Warhammer: HORUS HERESY: AGE OF DARKNESS DICE SET]【あす楽対応】 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/marchenshop/cabinet/tamago/12269104/imgrc0082067761.jpg?_ex=128x128)
![ねんどろいど 葬送のフリーレン フリーレン 修業時代Ver.[グッドスマイルカンパニー]【送料無料】《07月予約》 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/amiami/cabinet/pb/2026/062/figure-198092.jpg?_ex=128x128)



![ねんどろいど ウマ娘 プリティーダービー スーパークリーク[グッドスマイルカンパニー]【送料無料】《08月予約》 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/amiami/cabinet/pb/2026/082/figure-198782.jpg?_ex=128x128)

![ねんどろいど HYDE[グッドスマイルカンパニー]【送料無料】《08月予約》 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/amiami/cabinet/pb/2026/092/figure-199019.jpg?_ex=128x128)






![【中古】[MIL] TASMANIAN TIGER(タスマニアンタイガー) モジュラーコレクター サイズM ベルクロ BK(ブラック/黒)(7283.040)(20150223) 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/6402/9/cg64029328.jpg?_ex=128x128)
![【中古】[MIL] TASMANIAN TIGER(タスマニアンタイガー) MP7用 シングルマガジンポーチ MC(マルチカム)(20150223) 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/6402/8/cg64028005.jpg?_ex=128x128)
![【中古】[MIL] TASMANIAN TIGER(タスマニアンタイガー) MP7用 シングルマガジンポーチ MC(マルチカム)(20150223) 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/6402/8/cg64028006.jpg?_ex=128x128)




![【ネコポス対応】EAGLE(イーグル)/092-GRT/ローターチューブ(64.5巾mmx2m)[グラファイトパーターン] 製品画像:5位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rc-yumekuukan/cabinet/eagle01/092-grt.jpg?_ex=128x128)



