特別企画
杉山淳一の「鉄道ジオラマ旅情」、第5回:愛知県名古屋市「リニア・鉄道館」[後編]
館長に聞く「ジオラマのコンセプト、制作、管理、そして未来」
2021年3月2日 00:00
所在地: 名古屋市港区金城ふ頭3-2-2
開館時間:10:00~17:30(最終入館は閉館30分前まで)
休館日:毎週火曜日(祝日の場合は翌日) 春休み、大型連休、夏休みは火曜も開館
入館料:一般・大学生1000円 小中高生 500円 3歳以上未就学児 200円
アクセス:名古屋臨海高速鉄道あおなみ線金城ふ頭駅から徒歩2分
前回に続き「リニア・鉄道館」をご紹介。館長の天野満宏氏のインタビューを通して、ジオラマのコンセプト、制作過程、メンテナンスなどの工夫を伺った。
リニア・鉄道館のジオラマは幅が約33メートル、奥行きは最大8メートル。路線バスが6台入る広さになる。コンセプトは「日本最大級のスケールで東海道新幹線を表現する」、「実物の新幹線のようなデジタル制御」、「多彩なフィギュアによる情景描写」、「造形や照明、運行車両で鉄道の24時間を再現」、「新幹線16両フル編成を快調に走らせる」だ。
レールの総延長は約1km。中央に名古屋市街、左手に京阪神、右手に関東を再現した。東海道新幹線と東海道本線が東西に貫き、中央本線が関東と中京圏、京阪神には環状線を配置する。奥には高山本線、手前には関西線・紀勢線に見立てたローカル線がある。線路は軌間16.5mmのHOゲージ、市販品を活用した。
車両は1/80~1/87と紹介されている。日本国内で流通するHOゲージ車両に共通する縮尺だ。新幹線の軌間は広く車体も大きい。在来線の軌間は狭く車体もひとまわり小さい。したがって、両者を同じ軌間で再現すると縮尺が変わる。もっとも、HOゲージでは気にならないサイズだ。
一方、建物についてはそれぞれ縮尺が異なり、大胆な遠近効果を施した。ジオラマ全体のスケール感を考慮したからだ。名古屋市が大きく見えて、東京や大阪の景色はコンパクトに収まる。そのバランス感覚も絶妙で、近寄ってみれば違和感がなく、その景色を知っている人は納得の仕上がりになっている。
この大プロジェクトの参加企業の顔ぶれもすごい。企画・設計・制作に「丹青社」。丹青社は博物館や企業パビリオンなどを手がける会社で、本連載では「敦賀赤レンガ 倉庫 ジオラマ館」や「山梨県立リニア見学センター どきどきリニア館」のジオラマを手がけた。
建物、人形、自走式自動車の仕掛けなど模型制作は「ヤマネ」。ヤマネは産業模型を手がける会社で、本連載で紹介した「四国 鉄道文化館 南館」のジオラマがヤマネの作品だ。ジオラマシステム制御は「岡本電子」。背景画は前回も紹介した「アトリエ雲」。演出照明は「KAMEDEN」。映像と音響は「NHKエンタープライズ」と「東成社・サイバープランニング」が参加している。
博物館のプロジェクトは2007年に始まり、計画で2年、製作に1年を費やした。館長の天野氏は、当時、担当課長としてジオラマを担当し、各部門のエキスパートを束ね、プロジェクトをまとめた。デジタル制御を駆使して、毎朝、ボタンを1回押したら、1日14回の演出運転が進行し、閉館までに終了する。最初の段階からそのコンセプトだったという。今回は「ジオラマだけ」という取材にもかかわらず快く応じてくださり、たっぷりお話を伺えた。
人気の車両が走るだけのレイアウトにしたくなかった
今回は、筆者が質問して答えてもらうと言うよりも、館長が想いを語る口述筆記という形になった。そのため、ここから先の文章は、館長の言葉、という感じで記述していきたい。
「このジオラマでもっとも訴えたかったことは、鉄道の24時間です。新幹線が快調に走っている様子をご覧いただきたい。だけど、新幹線は在来線とネットワークを構成しています。新幹線が走る前に在来線が走っていて、新幹線が走り出し、リニアも試験走行して。夜中に新幹線が止まった後もサンライズが走るシーンがある。保線作業もある。
朝昼夜の演出には照明が重要です。東京の空の朝焼けから明るくなっていきます。ジオラマの照明は、蛍光灯の時代は青や赤のセロファンを貼って、色の組み合わせで変化させていたんです。舞台照明と同じですね。あれは地面を見ている分にはいいんですけど、ふと上を見上げると興ざめしちゃう。だから、基本的にパッと見たときは照明が見えない天井にしました。ライトがあるのかなあぐらいですね。
2点目のポイントは、列車以外の仕掛けです。鉄道模型が動いているのは当たり前で、それ以外に動くものを随所に入れたかった。JR東海バスが駅前を走るとか 消防車が火災現場に急行している。とにかく車両以外に動くものをたくさん。保線作業員が出たり入ったり、そんなからくりがあったら面白いね、と。
ドイツのミニチュアワンダーランドを見学したら、大人が食い入るように見ている。しかも高いお金を払って見に来てくださる。それだけのスケールがあるんですけどね。うちはそうもいかないから、なるべくアップダウンをつけて立体的に見せようと。最初は今の1/3ぐらいの大きさで考えていたんですけど、計画段階でジオラマを大きくしようという話になって現在のサイズになりました。
3つ目が子供目線。ジオラマを楽しもうとすると子供の目線は低いでしょう。事務机よりちょっと低い高さ、650mmでベースを作って、そこから上へ山を作り、少し掘り下げてトンネルを走らせる。広さは限界があるから、レイアウトは上がったり下がったり曲がったりというのを組み合わせました。
盛り込む要素、レールや建物の配置を決めて、図面ができた段階でスタディー模型を作りました。本物の1/15くらいのサイズで。それを使って、CCDカメラを目線の高さにおいて、子供と大人の目線で見た時にどう見えるか確認したんです。もうちょっと山を高くしようとか、いろいろな議論をした記憶があります。このスタディー模型は倉庫で保管しています。背景画を書いてくださった島倉さんの原画もあります。いずれジオラマに関する特別展を企画して見ていただこうと思っています。
「ノンスケール」が合い言葉
レイアウトの設定については、東海道新幹線沿線で何を強調すべきか、というネタ出しから始めました。実際に写真を撮りに行って、それをいったんイラスト画にする。そのイラストを元に建物や情景、フィギュアを作っていきました。
情景の出発点は名古屋駅ビルのJRセントラルタワーズです。でも、HOゲージの縮尺で作ると、天井を突き抜ける高さになってしまう。そこでもう建物や景色については「ノンスケール(正縮尺否定)」という割り切りをしました。タワーズの大きさを決めたら、周辺の高層ビルも高くするかというと、そっちは低くていいよと(笑)。
手前に高層ビルがあると、ジオラマの奥にせっかく作ったものが見えづらい。島倉さんの背景画も見えなくなってしまう。JR東海が作るジオラマだし、他社の建物には意匠もある。スケールも違うし、なんとなく似ていればいいだろうと割り切りました。精緻に作った建物はセントラルタワーズと、当社の在来線の指令がいる太閤ビルくらいですね。
その高層ビルの後ろの街並みを新幹線が高架で走ります。こんなところに新幹線のレールはないだろうという意見もあったんです。でも私は企画の責任者として「これは新幹線を見せるためのジオラマだから、実際とは違う配置だとしても、高架線で新幹線が快調に走る姿を見せなきゃだめだ」と言いました。
本当は東京駅も新大阪駅も作りたかったけれど、この広さがあっても無理なんです。名古屋駅だけ作るだけでもあんなに大きいんです。もう新幹線については名古屋駅だけにしようと。東京、大阪とも建物は小さいんです。大きく作りすぎると演出できる景色が減ってしまうので、建物を低くして、より多くのものを再現したかった。
たとえば東京の景色。小さな建物をたくさん用意しましたけど、新橋の駅前はこだわりました。毎日、全国ニュースでサラリーマンへのインタビュー映像が出ますから。東京スカイツリーは当館がオープンする時に話題になっていたので作りました。最初は背景画にしようと思ったんです。でも立体模型を急遽作ってもらったんですね。お台場も含めて、夜景で生えました。作って良かったなと。ヘリコプターも飛んでいるんですけれど、本当は動かしたかった。飛行機も飛ばしたい。でも鉄道が主体なので、そこまで頑張らなくてもいいかな、と。
レール配置は勾配とメンテナンスを考慮
ジオラマの全体像が固まってから、JR東海浜松工場という、東海道新幹線の車両の検査、修繕施設があるんですけど、その体育館でレールを仮組みして実際に走らせました。耐久試験もやりましたよ。真夏の暑い時に1週間ぐらい。新幹線の速度をどのくらいにするか、それに合わせて在来線の速度を決めました。その速度でどのくらいの勾配に耐えられるか。実際の鉄道のような走行試験をしました。
メンテナンスについても設計段階で織り込み済みです。ジオラマと観客の間はガラス張りにしなかった。そのほうが見やすいし、光の演出が反射してしまう。だけどその結果として埃が溜まりやすくなります。だから月に一度、ジオラマ全体を掃除します。レイアウトのなかに、人が出て対応ができるスペースと、人が歩ける場所もある。たとえば気球を浮かせているところがそれです。
レールは毎朝、全線を清掃しています。レールクリーニング車両を作って、機関車に繋いで動かしています。特に「ここは危ないぞ」というところは手で磨きます。どうしても調子が悪いな、という場所は交換していますけれども、いままでポイント部分くらいかな。カーブレールの外側は片減りするかな、と思っていましたが、いまのところ交換していません。線路にはとてもこだわっていて、電化区間はすべて架線を張っています。これはダミーで通電していないんですけど、電化区間の風景には絶対に必要なので。
演出面では、CCDカメラを取り付けた車両を走らせて、モニターに映像を出した。車両に映像送信用のアンテナを付けて、受信状態もチェックしました。運行管理用のデジタルコントロールの受信装置ですね。新幹線と在来線が指令システムに基づいてきちんと動くかどうか。車両側のデータ受信装置が、最初に選定したチップがダメで、別のメーカーに交換したら動いた。これも事前に確認できて良かった。工場でブロックごとに分割してジオラマを作っていきます。ここまでを浜松工場で確認して、リニア・鉄道館に運んで組み立てました。
市販の車両を改造、定期点検を実施
車両数は400をちょっと超えるくらいあります。1回の演出で動かす車両は170両ほど。新幹線の16両編成が6本、そこに在来線が加わります。1日に20分の演出を14回やりますので、性能が落ちるとスピードが出なくなって、運行時間がズレていきます。新幹線の1編成16両にはモーター付き車両が6両あるんです。この6両が同じ性能を持たないとスムーズに走らない。運行管理は実物の新幹線のデジタルATCのイメージでプログラムされているので、列車の運行間隔は維持されて衝突はしません。しかし演出は止まってしまう。
そこで、車両の個体差を出さないように、定期的にメンテナンスをしています。そのための専任のスタッフが常駐しています。走行距離というより、日数管理ですね。車種や部品、摩耗状況等によって交換周期は異なりますが、新幹線を例に挙げると、1ヵ月に1回モーターの交換をしています。市販品の車両も、耐久性を高めるため改造してから運用を始めます。全ての車両がきっちり管理されていて、個体差を出さないように作業してもらっています。実際の新幹線車両も浜松工場で定期メンテナンスをしています。それと同じです。
ジオラマの10年の変化と、これから
この10年で大きな変化はないですね。メンテナンスの踏み台となる畑のところに熱気球を追加したのが最初の変化だったかな。それから、2011年の営業開始時点ではJRセントラルタワーズ横のゲートタワービルが工事中でした。工事着手は把握していたので、工事現場と黄色いクレーン車を配置していました。ゲートタワービル完成と同時に、こちらも完成させました。あとは、スクリーンの演出で花火が上がったり、遊覧船の船が周遊するように改良したり。少しずつ手を入れていますけれども、大きな変化はなかったかな。
名古屋駅の地下にはすでにリニア中央新幹線の駅があります。ここは制作当時に実物の設計図がなくて、2面4線っていう配置だけでした。プラットホームが2面あって、その両側にそれぞれ軌道があって4線ですね。この部分は夜間開館イベントでお披露目したんですけど、ゲストが牧瀬里穂さんでした。彼女は東海道新幹線のCM「クリスマスエクスプレス」のヒロインというご縁がありまして、リニアのプラットホームに牧瀬さんのフィギュアを置いていいですかと許可をいただきました。
今後について、名古屋駅は名鉄さんが駅ビルを建て替える構想がありますけど、こちらで再現する予定はないです。JR東海のジオラマですから、新幹線とリニアさえしっかりと作れば目的は達成したと考えています。そこもキッチリ線引きをしていて、リニア・鉄道館は作りましたけど、名古屋駅と当館までを結ぶ「あおなみ線」はありません。JRグループですが貨物列車も走りません。いま、東海道新幹線の歴代車両を走らせるイベント中ですけれど、500系はJR西日本さんの車両なので置いていないんです。
JR東海の車両としては、在来線に新型車両の315系が導入されます。これは市販の模型化待ちかなあ。N700Sは東海道新幹線の新しい顔なので、半ば意地で特注しましたけれど。もし特注するなら、HC85系を検討したいです。特急「南紀」、「ひだ」のキハ85系を置き換える車両です。JR東海として、日本の特急列車用として初のハイブリッド車両ですし、試験走行が終わって量産化も決まったことですから。
文章にするとちょっと固い印象になってしまったけれど、天野満宏館長の人柄はざっくばらんで、一を聞くと十も二十も返ってくる。その言葉の奥に「これも見せたい」、「こんな仕掛けはどうだろう」という、鉄道への愛情を感じた。おとぎ話や保線のカラクリなどは愛嬌たっぷりな話しぶり。ぜひ、館長自らジオラマを語るイベントを開催してほしい。新幹線に乗って聞きに行く価値があると思う。









![グッドスマイルカンパニー[GOOD SMILE COMPANY] ねんどろいど ピクミン オッチン ノンスケール 磁石使用 プラスチック製 塗装済み可動フィギュア 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/41e2uUrKk4L._SL160_.jpg)

![ファット・カンパニー[Phat Company] ウマ娘 プリティーダービー ダンツフレーム 1/7スケール プラスチック製 塗装済み完成品 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/41oNyjmqcwL._SL160_.jpg)

![マックスファクトリー[Max Factory] ねんどろいどもあ 東方Project ゆっくりしていってね!!! ノンスケール プラスチック製 塗装済みフィギュア 製品画像:8位](https://m.media-amazon.com/images/I/41PPbgmtMTL._SL160_.jpg)











![BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ) 30MS オプションボディパーツ タイプMG01[カラーC] ノンスケール 色分け済みプラモデル 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/31b0bncR75L._SL160_.jpg)

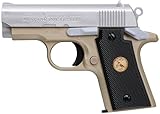
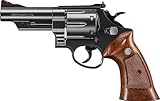










![ゴッドハンド(GodHand) 神ヤス! 10mm厚 3種類セットB [#600/#800/#1000] GH-KS10-A3B 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/41SoT5eE7fL._SL160_.jpg)
![武藤商事(Muto Syouji) MUTOSYOUJI [] プラリペア ブラック PL16B【HTRC3】 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/51Hn79+nVuL._SL160_.jpg)






![HGUC 1/144 機動戦士ガンダムUC(ユニコーン) クシャトリヤ プラモデル(再販)[BANDAI SPIRITS]《発売済・在庫品》 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/amiami/cabinet/images/2025/252/toy-gdm-7074.jpg?_ex=128x128)





![【中古】【未組立】1/144 HGUC MSK-008 ディジェ(ナラティブVer.) 「機動戦士ガンダムNT」 プレミアムバンダイ限定 [5057567]<プラモデル>(代引き不可)6546 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/wondergoo/cabinet/hobbytenpo148/654620250204109_1.jpg?_ex=128x128)


![グッドスマイルカンパニー ねんどろいど KAITO カンタレラVer.「KAITO」 ネンドロイド2973KAITOカンタレラVER [ネンドロイド2973KAITOカンタレラVER] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/edion/cabinet/goods/ll/img_549/4580828673717_1.jpg?_ex=128x128)
![【S.H.Figuarts】セル 第一形態 [2025年9月再販]『ドラゴンボールZ』新品 塗装済み可動フィギュア 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mintplus/cabinet/12442973/12442999/imgrc0140164854.jpg?_ex=128x128)

![ねんどろいど 劇場版 呪術廻戦 0Ver. 五条悟[グッドスマイルカンパニー]【1週間以内発送】 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/comi-choku/cabinet/im00042500/042833-01.jpg?_ex=128x128)

![POP UP PARADE NEEDY GIRL OVERDOSE あめちゃん L size 完成品フィギュア[グッドスマイルカンパニー]【送料無料】《発売済・在庫品》 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/amiami/cabinet/images/2025/401/figure-192118.jpg?_ex=128x128)



![タカラトミー OG-01 アイアンハイド OG01アイアンハイド [OG01アイアンハイド] 製品画像:20位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/edion/cabinet/goods/ll/img_549/4904810088783_1.jpg?_ex=128x128)





![【リアルタイプ】G&P GP090バレルロックナット/BK(黒・ブラック)★マルイM4/M16 シリーズ 検)サバイバルゲームトイガン電動ガン[全国一律300円配送可能] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/military-base/cabinet/a/gp/gp090.jpg?_ex=128x128)




![イーグル AS6420U-BK M4x6 アルミスペーサー 2.0mm厚(6個入)[ブラック] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/irijon/cabinet/22/imgrc0121370260.jpg?_ex=128x128)








