特別企画
ヘタ仙人の「プラモデルを楽しもう!」、筆塗りでよりキャラクター性を強くする!
2021年4月30日 00:00
どこに何を塗るかをしっかり考えておこう
では、準備も整ったところで作業を開始します。とはいえ、作業をする前に作戦会議はしたほうがよいでしょう。つまり、「どこに何を塗るのか?」を事前に決めておくということです。設定でカラーバリエーションの機体があったら、それにしてみる(とはいえ、今はカラバリ機体もリリースされていることが多いのですが)、そもそも自分オリジナルカラーでやってみる、など、いくつかやり方はあると思います。
プロモデラーだったり、経験豊富な人は、パソコン上で実際にシミュレートしたりもしますが、今回私が採った方法は……いきあたりばったり、です。まあ大抵の場合、色相環の補色関係にある色を塗るか、同系統でトーンを変えた色を塗ればそれっぽくなるので、パーツの成形色と合いそうな色を各所に塗っていこうと思います。
幅広い部分を筆で塗るには、厚く塗って削る!
ところで、今回は前述したように自分のパチ組みストックの中からひとつ引っ張り出してきました。ということは、シールも貼った状態です。色分けのシールは塗装ではなかなか表現しにくいメタリック調のものがあったりもしますし、そもそも便利ではあるので極力残す方法で作業を進めたいと思います。
とはいえ、肩のバインダーだけはどうしようかなと。大きな白いシールでパーツ全面を覆う仕様なのですが、実は制作当時あんまりうまく貼れなくて、シワができてしまっています。うーん、手始めに、ここを白く塗ろうかなと。
それにはシールを剥がさないといけません。シールは、貼ってから時間が経つとノリが意外とベタベタしていますから、丁寧に取り除きます。いったん剥がしたシールで、ペタペタと残ったノリを取り除き、指とティッシュでこすりました。が、本当は食器用の洗剤などで丁寧に落としたほうがよいです。
塗面をきれいにするのは塗装の鉄則なので。なお、塗料は薄めて使ったりもしますが、今回は薄めなくても意外と塗料が筆で伸びたので、そのまま使いました。もし塗料が粘液っぽくなっていたら、皿に塗料をとって、薄め液を少しだけ垂らしつつ調整してください。
写真の通り、ここはエンジ色のパーツに白い塗料を塗っていきます。が、実はけっこうこれが鬼門。濃い色のパーツに明るい色(白のほか、黄色や赤)を塗ると、透けるのです。模型雑誌などでは「発色していない」などと言います。
これを回避するには、本来は同色を何回か重ね塗りして発色させるのですが、その前に下地にサーフェイサーと呼ばれる下地材を塗布(スプレータイプやエアブラシで吹き付ける「ビンサフ」もあります)したり、透けにくい明るいグレーの塗料を先に塗ったりします。でも……面倒ですよね?
特に今回はスプレーは匂いもするのでパスしたいところですし、グレーを塗るのも筆塗りであれば塗膜が厚くなるし、なによりメンドイ。そこで、何度か白を塗り重ねるだけで、どうにか白くしました。
でも、塗り重ねたらマジでヤバい! ぼってりしてどーしようもない!
これ、ある程度筆塗りの宿命ではあるのですが、塗り方だったり塗料の薄め方でだいぶん変わってきます。私はこのあたりがヘタなので、もう、見た目がヤバいことになっていますが、実は修正する方法は、あるにはあります。それは、1200番程度の紙やすりで筆による凸凹をならしてやる方法です。
まあ、多少マシになった程度なのと、やりすぎて地肌が露出し始めていますが、あからさまな凸凹はなくなったかなと。これだけ大きな面積に明るい色をきれいに塗るというのは、なかなか難しいですね。
細かい塗装が楽しい頭部のディテールアップ
さて、気を取り直して、次は頭に行ってみましょう。頭は、けっこう複雑な形状をしていて、部分塗装が楽しい箇所です。
しかも、先程と違って塗る面積が小さいので、筆ムラなどが起こる可能性は低い……というか、筆ムラがあっても気づかれにくいレベルです。
さてこの機体、頭頂部に突起があり、側面にも突起があるので、このあたりを違う色にしてあげると細やかさが増しそうです。やってみましょう。
うーん、もう一声ほしいところ。そこで、ツノの先に銀とクリアレッドを混ぜたメタリックなピンクをチョンと付けてみました。













![グッドスマイルカンパニー[GOOD SMILE COMPANY] POP UP PARADE ウマ娘 プリティーダービー ネオユニヴァース L size ノンスケール プラスチック製 塗装済み完成品 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/41Xt56zQ3CL._SL160_.jpg)








![BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ) 30MS SIS-E00 ミャスティ[カラーC] ノンスケール 色分け済みプラモデル 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/416LIRWNpkL._SL160_.jpg)
![BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ) 30MS オプションボディパーツ タイプMG01[カラーC] ノンスケール 色分け済みプラモデル 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/31b0bncR75L._SL160_.jpg)


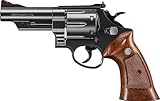


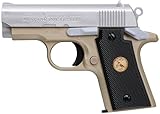







![ゴッドハンド(GodHand) 神ヤス! 10mm厚 3種類セットB [#600/#800/#1000] GH-KS10-A3B 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/41SoT5eE7fL._SL160_.jpg)
![武藤商事(Muto Syouji) MUTOSYOUJI [] プラリペア ブラック PL16B【HTRC3】 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/51Hn79+nVuL._SL160_.jpg)











![レゴ(LEGO) テクニック オフロード・レースバギー 42164(1個)【レゴ(LEGO)】[おもちゃ 玩具 プレゼント 8歳 9歳 10歳] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/netbaby/cabinet/167/5702017567167.jpg?_ex=128x128)






![エヴァンゲリオン(RADIO EVA) 式波・アスカ・ラングレー Ver.RADIO EVA Part.2 1/7 完成品フィギュア(再販)[ホビーマックスジャパン]《11月予約》 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/amiami/cabinet/pb/2021/501/figure-134609.jpg?_ex=128x128)
![【中古】[FIG] ヒロインメモリーズ 鮎川まどか きまぐれオレンジ☆ロード 完成品 フィギュア メガハウス(20160916) 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/6123/0/cg61230903.jpg?_ex=128x128)











![HELIKON-TEX ショルダーバッグ Carryall デイリー TB-CRD-PO [ PLウッドランド ] ランドリー袋 ランドリーケース 洗濯物入れ 洗濯袋 洗濯用袋 洗濯バッグ ランドリーポーチ 脱衣袋 衣類収納バッグ 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/revolut1/cabinet/c358/8_tbcrdpo04_600.jpg?_ex=128x128)




 製品画像:17位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/hobby-online/cabinet/_rc/eagle_racing/4534182631012-1.jpg?_ex=128x128)



![【送料無料】イーグル クロームボディクリップ(ショート小)[PU]+ワッシャー&リーシュ(4ケ) 品番3537-PU 製品画像:13位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/auc-kite/cabinet/02937440/eagle02/imgrc0064417317.jpg?_ex=128x128)
![HOBBYWING ESCクーリングファン [10BL120用]【ホビーウィング日本総代理店】 製品画像:12位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/sekido/cabinet/04682850/06835784/1030860003.jpg?_ex=128x128)
 製品画像:11位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/hobby-online/cabinet/_rc/kyosho-18/4548565311224-1.jpg?_ex=128x128)

