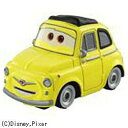特別企画
ヘタ仙人の「プラモデルを楽しもう!」、紫のスミ入れが効果的! 「HG 1/144 ペーネロペー」を部分塗装してみる
2021年5月27日 00:00
ガンダムファンにとって、マストで観るべき映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」。原稿執筆時点では公開延期の状況となっていますが、ガンプラはすでに発売済み。今回取り上げる「HGUC 1/144 ペーネロペー」は、ハサウェイ関連ではトップバッターとして、2019年10月に発売されました。
新製品としては4月に発売された「HGUC 1/144 Ξガンダム」や、「HGUC 1/144 ΞガンダムVSペーネロペー ファンネル・ミサイル エフェクトセット」が話題ですが、今回はあえて、ティザー映像が公開された時期から異形のMSとして印象的だったペーネロペーを作りたいと思います。
作業については、前回、前々回同様に、部分塗装をやっていきます。使う塗料はこれまで同様、GSIクレオスの水性塗料「水性ホビーカラー AQUEOUS」シリーズ、そしてガンダムマーカーと、一部タミヤのエナメル塗料です。特にどの塗料で実行しても問題はないのですが、それぞれ特性が違いますので、記事末に記載しておきます。塗料の特性に慣れてしまえば、適宜使い分けをしてラクな方法で塗装をすることができるようになりますので、いろいろな塗料を試すのも楽しいですよ。
今回使用する塗料について
・GSIクレオス ガンダムマーカーシリーズ
ガンプラ用に開発されたペン型の塗料。ペンなので初めての方にはオススメ。広い面積に塗る場合は、ペンだと大変なので、塗料皿に中身を出して筆塗りすることも。筆は、ラッカー系シンナー(匂いあり)で洗えばきれいになります。
・GSIクレオス 水性ホビーカラー AQUEOUS
水で筆洗いが可能。当然水で塗料の濃度を調整できるが、薄くしすぎるとプラモデルが弾いてしまうので、薄める場合は専用の「水性ホビーカラー専用薄め液」を使う。
・タミヤ エナメル塗料
エナメル塗料 (※1) は、ガンプラに限って言えばスミ入れ (※2) に使われることが多い。いったん塗装しても、拭き取りが楽という特徴がある。ただし、プラスチックの地肌に極薄のエナメル塗料を流し込むと、パーツが割れてしまう危険性がある。ゆえに、パチ組のキットへのスミ入れ(およびウォッシング)は危険。ただし通常の濃度で塗装したり、関節やダボなどの圧力のかかっている箇所以外であれば、使える。
(※1)エナメル塗料:プラモデル用の塗料にはラッカー、水性、エナメルなどの種類があり特性が異なります。エナメルはスミ入れに適している一方で、含まれるシンナーがテンションのかかった部分に染み込むとプラスチックが割れることがあります
(※2)スミ入れ:プラモデルに彫り込まれたパネルラインなどのミゾ(モールド、スジ彫りなどといいます)に塗料を流し込むことで形状を強調する手法。
さてどう塗るか? 未塗装を眺める
今回ペーネロペーを選んだのは、とにかく映像がカッコいい。ティザーではまるでドラゴンのように飛んでいて、これまでのモビルスーツとは一線を画する動きをするうえに、形もΞガンダム以上に異形感があり、そしてデカい! 作りごたえも十分です。
そもそもペーネロペーという機体がどういうものかと言いますと、主人公であるハサウェイ・ノアたちの反地球連邦組織「マフティー・ナビーユ・エリン」の捕捉殲滅を命じられたキルケー部隊に配備されたモビルスーツです。その特徴は、ミノフスキー・フライト・ユニットを装備して、地球上で単体での飛行が可能になっていること。そして、「大きい」ことです。
物語の舞台となるU.C.105年は、「機動戦士ZZガンダム」のU.C.0088から続くモビルスーツの大型化が極まった時代であり、ペーネロペーも頭頂高が26mにも及びます(あのユニコーンガンダムですらユニコーンモードで21m強です)。そしてもちろん、横幅もトンデモなく大きいのです。なお、対するΞガンダムもミノフスキー・フライトを行いまして、ペーネロペーとΞガンダムは兄弟機的な位置づけとなっています。
まずは例によって、実作業の前にパチっと組んだペーネロペーを眺め回してみます。
と、正直なところ、これを部分塗装するのはツラい! 組んだだけで白ベースの機体が美しく、これに自分なりのカラーリングを、というのも、なにか違う気がします。以前取り上げたズゴックなどは、それこそ40年にわたって様々な人がいろいろなアレンジ作り続けた機体なので、自分流にアレコレ楽しんでもまあ、許容範囲は広い。
しかしペーネロペーは最新キットであって、全面塗装して「俺ペーネロペー」にしてしまい「面白いねー」という方向に持っていくならばまだしも、一部だけ色を変えてもセンスの問題がつきまとい……。いわゆる「なんかヘン」になる可能性がきわめて高いのです。
熟考に熟考を重ねた結果、私がたどり着いたただひとつの結論、それは……
ムリ! いきあたりばったりでやろう!
というものです。そもそも設定画と違うカラーリングをしようと考えた段階でセンスの問題はつきまといますし、正直素人ではどうしようもない。ならば好き勝手に色を塗って楽しんでしまおう! 自分が買って自分で作るものなのだから誰にはばかる必要もないでしょう、ということです。どうせ塗り終われば、自分が作ったものですから好きになっちゃいます。それがまた、プラモデルの楽しいところでしょう。
とはいえ。
とはいえ、あまりにもテキトーに塗るのは、それはそれで面白くない。肩の力を抜いたところで、ある程度の方向性を決めました。それは、「なるべく機体の純白さを失わないように、ディテールをなんとか際立たせたい」という願い(もはや計画ではなく、願い)です。
ただし朗報もあって、このペーネロペー、けっこうディテールが細かい箇所が多いんですね。モールド (※3) も入っていて、HGではありながら細密な箇所もあります。
そこで、こうしたモールドや細かい箇所に色を付けていけば、(たぶん)それなりになるだろう! という目論見です。なお、オリジナルでカラーリングをする場合、パソコンを使ってシミュレーションをする方もいらっしゃいますので、興味のある方は試してください。私の場合は、「アレ? この色を塗ったらこんなになるのか! 面白い!」的な楽しみも味わいたいので、敢えて結果がわかるようなことはしていません。
それに、メンドクサイ。結果がわかっちゃううえにメンドクサイ、さらに言えば、パソコンでシミューレーションしたイメージ通りの色になるかどうかは、これまた微妙な問題でもあり、ならばせっかくのプラモデルですから、自由にやってしまおうかなと。
(※3)モールド:プラモデルのパーツ表面に施された小さな突起や凹みで、パネルラインやリベット(ネジの頭)などを形作っている。モデラー間では、「モールドが細かい」、「モールドが甘い」といった会話が行なわれる。
まずは「オデュッセウスガンダム」のスミ入れ……全部スミ入れしてしまえ!
さて。ペーネロペーという大物を扱うにあたり、形態が多くて多少混乱したのは上記の通り。ここで思い起こすのは、ビジネス書によく書かれている「課題の切り分け」というやつです。全体のボリュームに右往左往せず、ひとつひとつ目の前の作業に集中してみようということで、まずはフィクスド・フライト・ユニット(以下、FFU)はおいておいて、オデュッセウスガンダムから手を付けることにしました。
全体のバランスは、オデュッセウスガンダムとFFUで同じ色を使えばちぐはぐにならずに済むかなと。また、オデュッセウスガンダムを先に塗り終わることで、それを基準にFFUの色を決めていくこともできるだろうという目論見もあります。
まず行なったのはスミ入れです。
「え? スミ入れって塗装の後にするのでは?」と思った方、そのとおりです。そのとおりなのですが、今回は自分でオリジナルの色を塗るわけなので、影響の大きい作業→小さい作業のほうが、イメージが把握しやすいかなと。よって、まずは全体の雰囲気を大きく変えるスミ入れを先にして、局地戦(部分塗装)は後から行おうという作戦なのです。
そして、スミ入れに使う色は、通常の黒やグレーではなく、紫にしました。実は紫は、ユニコーンガンダムなどでよく使われるスミ入れの色で、プラモデルのファンには定番にもなっています。もちろんこのあたりは自分の好みで色を変えてもいいと思います。
紫のスミを入れるにあたって、考慮すべきは塗料ですね。ガンダムマーカーのスミ入れペンは、ブラックやグレーはありますが紫はありません。また、以前紹介したMr.ウェザリングカラーに「フィルタ・リキッド レイヤーバイオレット」という商品もありますが、今回は手持ちもなく断念。
そうなると、ガンダムマーカーの紫を塗って拭き取ってもいいし、エナメルの紫を使うか、という選択肢になりますが、今回は水性ホビーカラーで色を自作しました。具体的には、水性ホビーカラー49番の「すみれ色」に、若干赤や青、黒を混ぜて調整し、薄め液でサラサラにしています。
ガンダムマーカーを使わなかったのは、そもそもスミ入れ塗料ではないので、毛細管現象を使えずモールド全部を塗ってから拭き取らねばならず、拭き取りが面倒かな、と思ったからです。
では作業を。「紫でスミ入れをしよう!」と決めた後は、一旦組んだオデュッセウスガンダムを作業しやすいようにバラバラにします。
ではスミ入れを始めていきましょう。作業自体は簡単で、単に塗料を筆にとってモールド(彫刻されたミゾ)にチョン!と触るだけ。塗料の濃度をサラサラにしているので、そのまま毛細管現象でサーッとモールドに流れていきます。
当然筆を付けた箇所は筆の跡が残りますが、これは後々、塗料が乾いたら拭き取ればよいのです……が、あまりにもはみ出している場合はまだ乾かないうちから綿棒で少し吸い取ると、乾いた後の拭き取り作業が楽になります。やりすぎるとせっかくモールドに流れ込んだ塗料も吸い取ってしまいますのでご注意を。
なお拭き取りは、水性ホビーカラーなので、その専用薄め液でOKなのですが、今回はより強力なラッカー系の薄め液を使用しました。匂いが嫌な方は、水性予備ーカラー専用薄め液で拭き取ってください。
お次は頭に行ってみましょう。顔部分は細かいので、スミ入れをするだけで映える箇所。ですが構造が複雑なので、バラさないといけません。パーツ同士の接合部にカッターの刃を入れて、ゆっくりゆっくり怪我をしないようにこじ開けていけばよいのですが、今回はホームセンターで見つけた道具を使ってみました。それがこちら。
ここまで来て、目に止まったのは脚部です。白基調の脚部はたいへん美しく、このままでもいいかな、と思ったのですが、やっぱりちょっと、いたずら的に色を入れてみたい。そこでこちらも紫でスミ入れをしようと思ったのですがちょっと待てと。脚部のモールドは他の箇所と違って幅広です。
このままスミ入れをしても、薄い塗料ですからムラができる可能性100%。そこで、ここはガンダムマーカーの出番かなと。ガンダムマーカーのペン先をモールドに沿って移動させ、スミ入れというよりはスミ“塗り”をしてみました。拭き取るのはスミ入れと同様です。
こうしてスミ入れを進めてきたのですが、やっぱりいいですね! プラモデルがどんどん精密に見えてきて。というわけで、先ほどは課題の切り分けだなんだと言っていましたが、スミ入れが楽しくなってきたので、このままFFUもスミ入れしてしまうことにしました。楽しいこと優先で作業を進めます。
こうしてスミ入れを進めてきたのですが、やっぱりいいですね! プラモデルがどんどん精密に見えてきて。というわけで、先ほどは課題の切り分けだなんだと言っていましたが、スミ入れが楽しくなってきたので、このままFFU(フィクスド・フライト・ユニット)もスミ入れしてしまうことにしました。楽しいこと優先で作業を進めます。
これにてスミ入れは終了です。FFUも含めて作業したので、これだけで実はけっこう時間がかかりました。時間がかかったということは、それだけプラモデルも外観が変化したということです(まあ、時間だけかかってあまり代わり映えのしない作業も存在していますが)。
つまり、「スミ入れだけでもペーネロペーは十分楽しめる」ということでもあります。ここから先は部分塗装を紹介しますが、ちょっと敷居が高いな、という方は、紫ではなくて黒でもグレーでも構いませんので、スミ入れだけでも楽しんでみてください。
とはいえ今回は「部分塗装」こそがメインテーマです。ダクトやヒザ、鮮やかな赤のラインなど、部分塗装でカッコ良さが大きく変わってきます。まずはオデッセウスガンダムの部分塗装をしていきます。
(C)創通・サンライズ












![マックスファクトリー[Max Factory] ねんどろいどもあ 東方Project ゆっくりしていってね!!! ノンスケール プラスチック製 塗装済みフィギュア 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/41PPbgmtMTL._SL160_.jpg)








![BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ) 30MS SIS-E00 ミャスティ[カラーC] ノンスケール 色分け済みプラモデル 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/416LIRWNpkL._SL160_.jpg)
![BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ) 30MS オプションボディパーツ タイプMG01[カラーC] ノンスケール 色分け済みプラモデル 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/31b0bncR75L._SL160_.jpg)


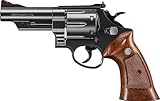

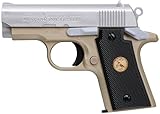



![ベルソス(VERSOS) VERSOS エアーガンセット Colt1911モデル & M4 R.I.Sモデル [ VS-C-M4 ] / M4モデル コルトモデル エアーガンキット エアガン サバイバルゲーム サバゲー アウトドア ブラック 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/417Q7MgkNCL._SL160_.jpg)




![ゴッドハンド(GodHand) 神ヤス! 10mm厚 3種類セットB [#600/#800/#1000] GH-KS10-A3B 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/41SoT5eE7fL._SL160_.jpg)


![武藤商事(Muto Syouji) MUTOSYOUJI [] プラリペア ブラック PL16B【HTRC3】 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51Hn79+nVuL._SL160_.jpg)












![HG 1/144 ガンダムデスサイズ [クリアカラー] 新機動戦記ガンダムW(ウイング) 製品画像:12位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/zootrope/cabinet/08019852/imgrc0163074040.jpg?_ex=128x128)


![ねんどろいど 文豪ストレイドッグス 太宰治(再販)[オランジュ・ルージュ]《05月予約》 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/amiami/cabinet/pb/2025/431/figure-193205.jpg?_ex=128x128)








![NB-61■【P.BERETTA刻印 M92FS仕様に】GUARDER M9&M92 グリップパネル 2016Ver マルイ KSC■ガスブロ用 リアル化に[全国一律300円配送可能] 製品画像:17位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/military-base/cabinet/a/item11/nb-61.jpg?_ex=128x128)