特別企画
タミヤのRCカーに挑戦! 新マシン「1/10RC NSX 」を組み立て、”ツーリングRCカー”でレースを目指す!
TT-02シャーシ
2021年7月12日 00:00
初心者向きで拡張性も高いシャフトドライブ4WD「TT-02シャーシ」
RCカーは高速でコースを駆け抜けるため、ネジの緩みなどには気を付けて組み立てなければいけない。組み立てに使用した工具は、ペンチ2種類、ネジ止め剤、ノギス、プラスドライバー2種、ピンセット、タイヤ用瞬間接着剤、ハサミ、クラフトナイフ。さらにボディを加工するため、穴を開けるピンバイスと拡げるリーマーを使った。
組み立て前にまず、説明書をざっと読み、部品の確認と、組み立ての流れをつかむ。「TT-02シャーシ」は、車輪の前後の間隔である「ホイールベース」、シャーシと地面との距離の「車高」、車輪の左右の幅「車幅」の3箇所の位置を変更できる設計となっている。今回はまず最初の挑戦と言うことで「スタンダード」のポジションを選択して組み立てることにした。こういったカスタマイズ性は“本格的なレース仕様”だとを感じた。
また、レースを視野に入れているので最初からカスタムパーツを組み込むという選択もあったが、まず各部品の構造を理解したい、ノーマルパーツで組んでみて走ってみたい、と言うところから今回は見送った。極力説明書通りに組み立てていく事にした。
組み立ての流れは、まず、スパーギヤとプロペラシャフトを合わせて、「バスタブ型」と呼ばれるフレームに組み込む。この構造により、モーターの力を前後の車輪に伝えることができる。続いて、前後のデフギヤを作る。樹脂で成形されたギヤを使うので、ランナーから切り離した跡が残らない様に気を付ける。
アッパーアームはフロントとリアでパーツの形が違うので、バスタブの形で前後を確認して間違えない様に組み立てていく。
前後のギヤボックスがシャフトドライブで繋がったら、モーターを取り付けていく。今回はキット付属の540モーターをそのまま使用した。
タイヤを取り付けるアップライトを組み立てたら、続いて4本のダンパーに進む。オイルを使わないスプリングタイプで、ハメ込み式なので簡単だ。前後に各2本づつダンパーを付けたら、ステアリングワイパーを組み立てる。
次はアクセルワークを行なうスピードコントローラーと、ハンドリングを行なうステアリングサーボを組み込んでいく。今回の組み立てで面白かったのが、「エレクトロニック スピードコントローラー 04S」。このスピードコントローラーは“ブラシモーター”、“ブラシレスモーター”の両方に対応しており、使用するための“設定”が必要だった。
まずブラシモーターと、ブラシレスモーターはどう違うかを説明したい。ブラシモーターは内部に「ブラシ」と呼ばれる電極と、「コミュテータ」と呼ばれる整流子(回転電気スイッチ)を設け、その2つが接触して電流の切り替えを行ない、モーターを回転させる。
ブラシレスモーターは従来のモーターよりも構造が複雑だが、その名の通りブラシがない。ブラシはモーターが回転することで摩耗してしまう消耗品であり使用を重ねることでメンテナンスが必要になる。ブラシレスモーターはブラシをもたない構造であるためメンテナンスの手間が少なく、耐久性や回転効率に優れている。近年普及しているモーターで、タミヤでもアップグレードパーツとして用意されている。
ブラシレスモーターはスピードコントローラーも対応したものが必要となる。筆者も将来的に使いたいと考えているので、今回、ブラシレスモーターに対応した「エレクトロニック スピードコントローラー 04S」を用意したというわけだ。
「エレクトロニック スピードコントローラー 04S」は出荷時点では「ブラシレス」用に設定されている。このため、ブラシタイプであるキット付属の540モーターを使うためには、スピードコントローラーを設定する必要がある。この設定は新鮮だったので細かい手順を紹介したい。
具体的な方法としては、
1 「送信機の電源をONにする」
2 「セットボタンを押したまま」
3 「受信機のスイッチをONにする」
4 LEDが赤→緑→橙と点灯を繰り返すので、橙の時にセットボタンを離す。
5 LEDが橙→緑の交互点灯に切り替わるので、緑の時にセットボタンを押す。
これでブラシモードになるので、付属の540モーターでの走行が可能になる。
スピードコントローラを設定し組み込んだら、ステアリングサーボ、受信機、スピードコントローラーを両面テープでシャーシに固定し、タイヤを組み立てる。
タイヤはホイールの油を中性洗剤で洗い、渇いたらはめ込んでタイヤ用瞬間接着剤で固定する。
アップライトにタイヤを取り付け、ボディマウントやバンパーを付ければシャーシは完成だ。










![マックスファクトリー[Max Factory] ねんどろいどもあ 東方Project ゆっくりしていってね!!! ノンスケール プラスチック製 塗装済みフィギュア 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/41PPbgmtMTL._SL160_.jpg)












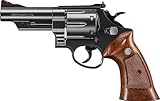


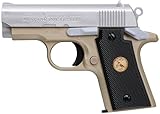








![ゴッドハンド(GodHand) 神ヤス! 10mm厚 3種類セットB [#600/#800/#1000] GH-KS10-A3B 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41SoT5eE7fL._SL160_.jpg)

![武藤商事(Muto Syouji) MUTOSYOUJI [] プラリペア ブラック PL16B【HTRC3】 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51Hn79+nVuL._SL160_.jpg)



![【中古】[MDL] ドリームトミカNo.145 1/61 AE86 トレノ(ホワイト×ブラック/ベトナム製) 頭文字D 完成品 ミニカー タカラトミー(20130921) 製品画像:14位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/6530/5/cg65305944.jpg?_ex=128x128)






![【スクウェアエニックス】ファイナルファンタジーVII ストラクチャーアーツ クラウド・ストライフ [プラスチックモデル キット]【2026年2月発売】[グッズ] 製品画像:7位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/neowing-r/cabinet/item_img_2176/neogds-938036.jpg?_ex=128x128)


![つぶらな瞳のお弁当箱 ぷちマスコットBC{ キーホルダー マスコット 玩具 おもちゃ }{ ギフト 誕生日 }{ 子ども会 施設 }[ 子供会 保育園 幼稚園 景品 イベント お祭り プレゼント 人気 ]【色柄指定不可】【不良対応不可】 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/tigercat/cabinet/shohin01/shohin_e/e21100/e21247_1.jpg?_ex=128x128)
![【中古】[FIG] 禪院直哉(ぜんいんなおや) 呪術廻戦 MAXIMATIC NAOYA ZEN'IN フィギュア プライズ(2789977) バンプレスト(20260127) 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/6603/1/cg66031598.jpg?_ex=128x128)
![【中古】[FIG] スルト アークナイツ ぬーどるストッパーフィギュア-スルト- フィギュア プライズ(AMU-PRZ20400) フリュー(20260116) 製品画像:20位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/6603/4/cg66034282.jpg?_ex=128x128)



![オカルティックソフビコレクション TVアニメ『ダンダダン』 ターボババア(招き猫)Ver.2 完成品フィギュア[メガハウス]《05月予約》 製品画像:16位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/amiami/cabinet/pb/2025/362/figure-191204.jpg?_ex=128x128)

![【グッドスマイルカンパニー】ねんどろいど 夏目友人帳 名取周一【2026年8月発売】[グッズ] 製品画像:14位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/neowing-r/cabinet/item_img_2166/neogds-968592.jpg?_ex=128x128)



![【半額・50%OFF】Barbie<バービー> リフレクター 4560182210339 バービー新入学・限定シリーズ <日本製> [M便 1/10] 製品画像:10位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/bunbougu-shibuya/cabinet/29/sb-ab013_01.jpg?_ex=128x128)
 製品画像:9位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/hobby-online/cabinet/_gun/marui-2/2000002846703-1.jpg?_ex=128x128)





![ZEXT ガンラック用棚板 天板フレーム BF90オプション[サバゲー サバイバルゲーム] 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/shunte/cabinet/hobby/zex003-00.jpg?_ex=128x128)
 製品画像:9位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/hobby-online/cabinet/_rc/tamiya-8/4950344511457-1.jpg?_ex=128x128)
 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/hobby-online/cabinet/_rc/tamiya-12/2000000088495-1.jpg?_ex=128x128)






